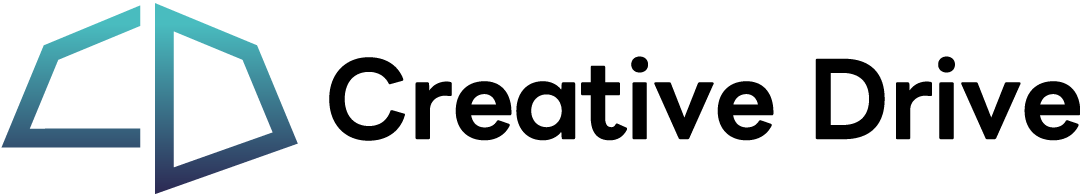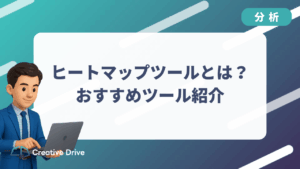ヒートマップツールおすすめ11選|初心者もわかる使い方と導入メリットも解説
2025年08月15日
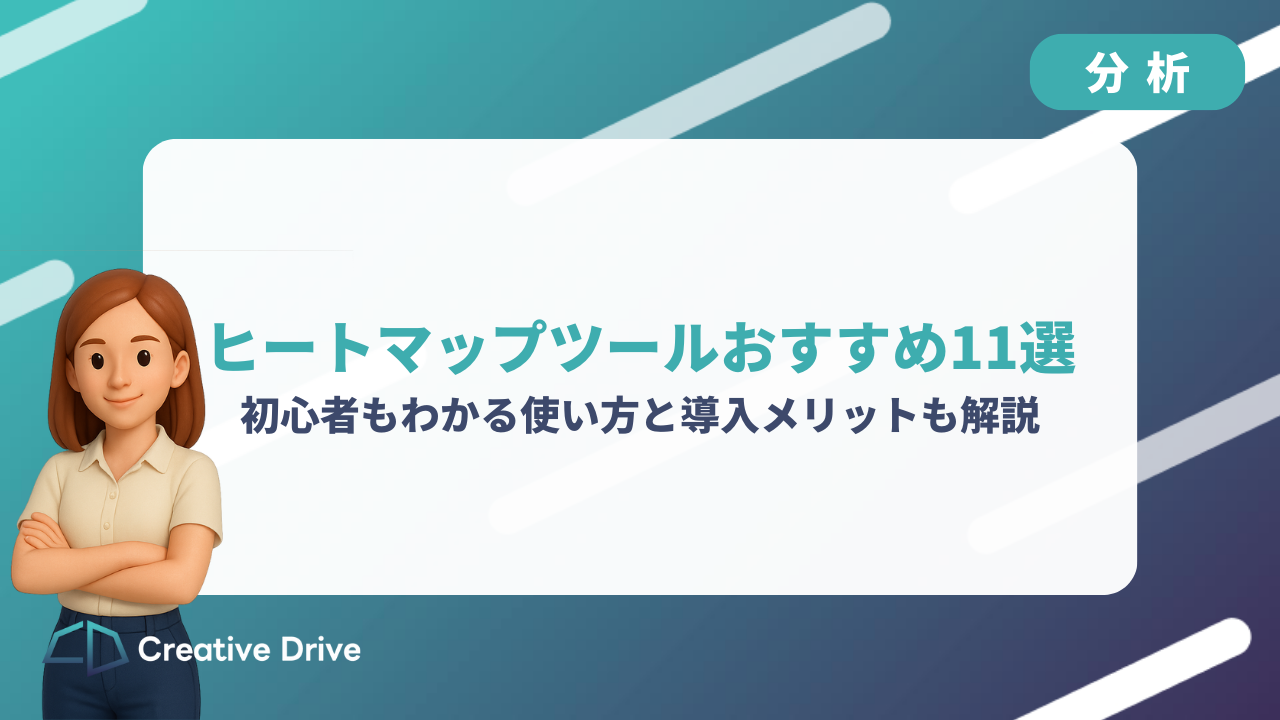
Webサイトを改善するためは、「どこが見られていて、どこが無視されているのか」を知ることが非常に重要です。そんなときに役立つのがヒートマップツールです。ユーザーの行動を視覚的に把握し、感覚では見抜けない課題を浮き彫りにしてくれます。今回は、ヒートマップツールの基本から導入メリット、おすすめのツールまで詳しく解説します。
目次
ヒートマップツールとは?

ヒートマップツールとは、ユーザーがWebページ上でどの部分を見ているか、どこをクリックしているか、どこで離脱しているかといった行動を可視化できるツールです。通常、クリック、マウス移動、スクロールの3つの観点からデータを取得します。ユーザーがどこに関心を持ち、逆にどのコンテンツがスルーされているのかを一目で把握できます。テキストやグラフでは伝わりづらい動きを“色”で見せるのが最大の特長です。
ユーザー行動を可視化する仕組みがある
ヒートマップツールは、JavaScriptのタグをWebページに埋め込むことで、ユーザーのブラウザ上の動作を記録します。記録された行動は、色の濃淡で視覚的に表示され、赤やオレンジが「よく見られている」、青は「ほとんど見られていない」ことを表すのが特徴です。この仕組みにより、視線やクリックの“熱量”をページ単位で確認できるようになります。導線の最適化やUI改善に欠かせない情報源といえるでしょう。
Webサイト改善にどう役立つのか
ヒートマップを活用することで、「なぜCV率が低いのか」「どこでユーザーが離脱しているのか」などの課題を視覚的に捉えることができます。たとえば、重要なボタンがスクロール圏外にある場合、それを視認できていないユーザーが多いことがわかります。また、コンテンツの読み飛ばしが多い箇所も検知可能です。数字だけでは判断が難しい「体感的な使いにくさ」を見つけ出せる点が、改善活動において大きなアドバンテージになります。
ヒートマップでわかる3つのこと

ヒートマップを活用すると、ユーザーがページ上でどのように行動しているのかを“視覚的に”捉えられます。ここでは、具体的にどんな情報が得られるのかを3つの観点から説明します。
クリックエリアの集中と無関心ゾーン
ヒートマップでは、ユーザーがどのエリアをクリックしているかが色で示されます。クリックの集中している箇所は赤く、あまり触れられていない部分は青やグレーで表示されるのが一般的です。リンク先への誘導が機能しているか、誤クリックが起きやすい場所はどこかなどが判断できます。また、思わぬ場所が頻繁にクリックされていた場合、“誤解を招く要素”として改善ポイントになることもあります。
スクロールの到達率・離脱ポイント
スクロール型ヒートマップでは、ユーザーがどこまでページを読んでいるかを把握できます。ページの上部は多くの人に見られますが、下に進むにつれて閲覧率が減少していくのが一般的です。赤から黄色、そして青へと変わる色のグラデーションを見ることで、どこが“読まれていない領域”なのかを視覚的に判断できます。重要なコンテンツやCTAボタンがスクロール圏外にある場合、配置の見直しが必要になるでしょう。
マウスの動き・滞在時間の傾向
一部の高機能ヒートマップツールでは、マウスの動きや滞在時間を視覚化することも可能です。ユーザーがマウスカーソルをどのあたりに長く置いているか、どのブロックで思考が止まっているかなどを推測できます。情報の読み込みに時間がかかっている箇所や、わかりにくさを感じているエリアの特定も可能。単なるスクロールやクリックだけでは把握しづらい「迷い」や「躊躇」を可視化できる点が大きな特徴です。
ヒートマップツールを使うメリット

ヒートマップツールは、ただ“見える化”できるだけではありません。Web担当者やマーケターにとって、施策の効率化や成果向上に大きく貢献するツールです。ここでは主な3つのメリットを紹介します。
感覚ではなくデータで改善できる
サイトを運用する際、「たぶんこうだろう」という思い込みで施策を進めてしまうことがあります。しかしヒートマップを使えば、実際のユーザー行動を視覚的なデータとして確認できるため、主観に頼らない改善が可能です。「このボタンは目立っているつもりだったが、誰も見ていなかった」といったギャップに気づけることで、無駄な施策を省き、的確な修正につなげることができます。根拠ある改善が、成果を加速させるのです。
ABテストやCVR改善との相性がよい
ヒートマップで得たデータは、ABテストの仮説立案にも役立ちます。たとえば「Aパターンのページではファーストビューに注目が集まりやすい」などの傾向がわかれば、テスト対象の要素を絞り込みやすくなります。また、コンバージョン率(CVR)が低いページの改善策を練る際も、ユーザーがどこで離脱しているかを可視化が可能。そのため、ボトルネックの特定が容易になります。施策の精度とスピードを両立できるのが大きな魅力です。
初心者でも視覚的に理解しやすい
ヒートマップは専門的な知識がなくても扱いやすく、Webサイトの分析に不慣れな方でも直感的に状況を把握できます。色の濃淡で「見られている」「見られていない」箇所が一目でわかるため、数値ばかりのレポートよりも伝わりやすいのが特長です。チーム内で共有する際にも効果的で、関係者との認識のズレを防ぐ手助けになります。分析を“チームで進める”うえでも、導入しやすいツールといえるでしょう。
ヒートマップツールの選び方

ヒートマップツールは多種多様で、それぞれに特長があります。選び方を間違えると、うまく活用できずに終わってしまうこともあるでしょう。ここでは、自社に最適なツールを見極めるためのポイントを4つの視点から解説します。
分析対象を明確にする
ヒートマップツールは、すべてのページやデバイスに対応しているとは限りません。たとえば、スマートフォンに特化した動作確認が必要であれば、モバイル対応が強いツールを選ぶのがおすすめです。また、LPやECサイトのように構成が明確なページでは、ユーザーの集中行動を可視化できるツールが適しています。使用するサイトの種類と目的に応じて、対応範囲がマッチするかを確認することが選定の第一歩になります。
ツールの機能・視覚性・UIの違いを見極める
各ツールには独自の強みがあります。スクロールヒートマップやクリックマップに加えて、マウスの動きや動画再生機能が備わっているものも存在します。また、分析画面のUIや色の見やすさも重要です。使い勝手が悪いと分析が面倒になり、継続的な活用が難しくなります。無料トライアルやデモ画面を活用して、自分に合うUIかどうかを確認しておくことが、長期的な運用には不可欠です。
日本語対応やサポートの有無も確認する
海外製のヒートマップツールは高機能なものが多く、日本語のサポートや操作マニュアルがないこともあります。英語に不安がある場合や、社内共有をスムーズに行いたい場合は、国産ツールや日本語対応のものを選ぶのがおすすめです。導入時の初期設定やトラブル対応など、サポート体制の有無によって活用レベルに差が出るため、機能だけでなく運用サポートの充実度にも注目しましょう。
無料・有料ツールを比較する
ヒートマップツールには、無料で使えるものと有料のものがあります。無料ツールは導入ハードルが低く、初めての分析にも向いていますが、記録上限や機能制限がある場合も多いです。一方、有料ツールは継続的な改善やチーム共有に強く、機能の幅も広がります。選択の際は、費用対効果と活用目的を天秤にかけながら判断することが大切です。長期的に使いたいなら、試用後の乗り換えも検討するとよいでしょう。
ヒートマップツールおすすめ11選

ヒートマップツールは、導入の目的や分析したいサイトの種類によって選ぶべき製品が異なります。ここからは無料ツールから高機能なエンタープライズ向けまで、人気の12製品を特徴別に紹介します。
1. 無料で使える「Clarity(Microsoft)」
「Clarity(Microsoft)」は、Microsoftが提供する完全無料のヒートマップツールです。クリック・スクロール・セッション録画の3機能が使え、操作も非常に直感的なのが特徴。大量のアクセスデータにも対応できるスケーラビリティがあり、サイトの規模を問わず活用可能です。個人ブロガーや中小企業だけでなく、大手企業でも試験導入されています。広告表示などのマネタイズも一切なく、費用ゼロでここまで使えるツールは他にほぼ存在しません。
サービスURL:https://clarity.microsoft.com/
2. 180カ国以上が利用している「User Heat」
「User Heat」は、日本語完全対応かつ無料で使えるヒートマップツールです。クリック・アテンション・スクロールなど、基本機能をしっかりカバーしています。広告表示がありますが、個人や小規模事業者にとっては十分な分析が可能。タグ設置だけで利用でき、WordPressとの連携もスムーズです。UIがシンプルなので、初心者でもすぐに操作できます。無料ツールのなかでも“日本語UIで選ぶならこれ”といえる存在です。
サービスURL:https://www.hotjar.com/product/heatmaps/
3. 有料・無料プランがある「Ptengine」
「Ptengine」は、アクセス解析とヒートマップが一体になったツールです。無料プランでも訪問数制限の範囲内でクリック・スクロール・滞在時間などを把握できます。デザイン性の高いUIとダッシュボードが特徴で、チーム共有やレポート作成にも強みがあります。有料プランではCVファネルやイベント設定など、より深い分析が可能。中規模サイトの改善やEC向けのユーザビリティ検証にも活用されています。
サービスURL:https://www.ptengine.com/
4. 中〜大規模向けのツール「Mouseflow」
「Mouseflow」は、クリックヒートマップに加え、セッション録画・フォーム分析・フィードバック収集など多彩な機能を兼ね備えた高機能ツールです。ユーザーの行動をリアルタイムで確認でき、ファネル分析にも対応。特にフォーム離脱の可視化に強みがあり、LPやお問い合わせページの改善に役立ちます。サイト内の問題発見から改善案のヒントまで、幅広いニーズに応える万能型なのもポイント。導入にはやや英語力が必要ですが、学習コストに見合う価値があります。
サービスURL:https://mouseflow.com/
5. グローバル展開向けの「Hotjar」
「Hotjar」は、グローバルで人気のヒートマップツールです。セッション録画、クリック・スクロールマップに加えて、アンケートやフィードバックフォームも実装可能。UIが非常にシンプルで、初めてでも扱いやすいのが魅力です。英語UIですが視覚的な要素が多いため、英語に抵抗がある方でも直感的に操作できます。スタートアップから大手企業まで幅広く導入されており、特にLPの改善や顧客理解を重視する企業にもおすすめです。
サービスURL:https://www.hotjar.com/ja/
6. エンタープライズ向けの「Contentsquare」
「Contentsquare」は、大企業やグローバルブランドに導入されている、AI搭載の高度なUX解析ツールです。クリックやスクロールの可視化にとどまらず、ユーザージャーニー全体を定量的・定性的に把握できます。ヒートマップ以外にもエリアクリックや、セグメント分析、AIによる改善提案などが可能。開発からマーケティング、経営層まで一貫した分析ができます。高価格帯のツールですが、ROIを求める大規模サイトに適しています。
サービスURL:https://contentsquare.com/
7. CVR改善に特化した「SiTest」
「SiTest」は、ABテスト機能やEFO(エントリーフォーム最適化)と組み合わせて使える、CVR改善に特化したツールです。ヒートマップで見つけた改善点を即座にテスト施策に活かせるのが強みです。特にECサイトやLPの運用担当者に人気があり、コンバージョン改善の“実践ツール”として導入されるケースが多数。ヒートマップのデータを活かした施策立案〜実行までを1ツールで完結できる点が魅力です。
サービスURL:https://sitest.jp/
8. アプリ分析にも対応している「Smartlook」
「Smartlook」はWebサイトだけでなく、モバイルアプリのユーザー行動も可視化できる分析ツールです。セッション録画とヒートマップの連携がスムーズで、SPA(シングルページアプリ)にも対応しています。UIも洗練されており、イベント設定やフィルタ機能も直感的に操作可能。アプリとWebをまたいでUX改善を行いたい場合におすすめです。マーケターと開発者が同じ指標で会話できるようになるのも利点です。
サービスURL:https://www.smartlook.com/
9. 手軽に使える多機能ツール「Lucky Orange」
「Lucky Orange」は比較的リーズナブルな価格帯なのが魅力。ヒートマップはもちろん、チャットボットや、アンケート、レコーディング機能などを包括した多機能ツールです。リアルタイムで訪問者を確認したり、ユーザーの動線に沿った会話を仕掛けたりと、マーケティング×分析を融合させた設計が特徴です。中小企業やスモールチームでの改善活動に向いています。機能数に対してコストパフォーマンスが高く、入門用にもおすすめです。
サービスURL:https://www.bigcommerce.com/apps/lucky-orange/
10. マーケティング一体型の「Freshmarketer(旧Zarget)」
「Freshmarketer(旧Zarget)」はヒートマップだけでなく、ABテストやファネル分析、メールマーケティングまで統合されたマーケティングプラットフォームです。ユーザーの行動を基にした施策展開が可能。直感的なUIと、CRM連携が進んでいる点も特長で、BtoBサイトや中堅企業での導入が増加しています。1つのツールで「見る→試す→育てる」を完結させたい企業に向いています。
サービスURL:https://support.freshmarketer.com/support/home
11. ユーザー心理を探れる「Inspectlet」
「Inspectlet」は、セッション録画や詳細なクリックマップ、マウスの動きなどから、ユーザーの“意図”を読み取るのに長けたツールです。高いカスタマイズ性と、独自タグによるページ分岐設定が可能で、マーケティングのA/B検証やコピーの反応比較にも活用されています。直感ではわかりにくい微細な行動パターンを“見える化”するのに適しています。
サービスURL:https://www.inspectlet.com/
ヒートマップを導入する際によくある失敗例

ヒートマップツールは便利な反面、活用方法を誤ると効果が出にくい場合があります。最後に、導入後によく見られる失敗とその回避方法について解説します。
導入しただけで満足してしまう
ツールは入れただけで「改善できる」と思い込んでしまい、分析や施策に活かせないケースが多く見られます。ヒートマップはあくまで“気づき”を得るための手段です。導入後は定期的にデータを確認し、明確な目的に基づいて活用することが欠かせません。社内の運用ルールや担当者の明確化など、分析を継続できる仕組みを作ることも成功のカギを握ります。準備と実行がセットで初めて成果につながるのです。
ヒートマップだけに頼りすぎる
視覚的な情報が多く得られるヒートマップですが、それだけで判断を下すのはリスクがあります。たとえばスクロールの深さやクリックの密度だけでは、ユーザーの満足度や離脱理由のすべてを把握することはできません。Googleアナリティクスやサーチコンソールなどの定量データと組み合わせることで、より正確な分析が可能になります。ヒートマップはあくまで一部の視点であることを忘れず、他の手法と併用する意識を持ちましょう。
社内での活用・共有が進まない
せっかく得られた分析結果も、関係者に伝わらなければ改善は進みません。ヒートマップはビジュアルで直感的にわかりやすいという強みがある反面、誰か1人だけが見て終わってしまうこともあります。定例会議での共有やレポートへの反映、ツールのログイン権限の配布など、情報がチーム全体で活用される体制を整えることが必要です。社内全体で分析結果に関心を持ち、施策に反映する文化が重要となります。
まとめ
ヒートマップツールは、ユーザーの“見えない行動”を視覚化し、Webサイト改善に直結するヒントを与えてくれる強力なツールです。クリック箇所やスクロールの深さ、滞在傾向などを把握できることで、主観では見逃しがちな課題に気づくことが可能になります。ツールは数多く存在しますが、自社サイトの目的や分析スキル、運用体制に合ったものを選ぶことが重要です。そして導入して終わりではなく、得られた気づきを実際の施策に活かしてこそ、本当の価値が生まれます。