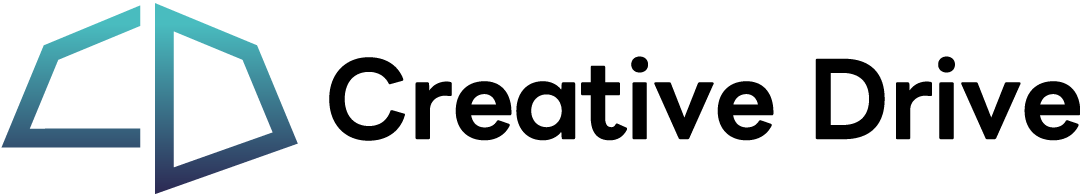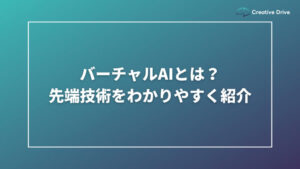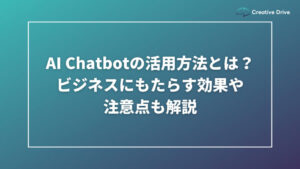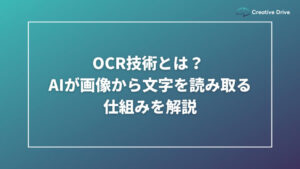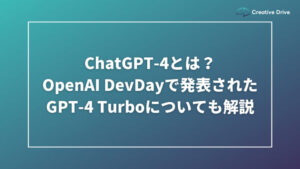AI
暗黙知とは?その活用方法を解説
2023年10月27日
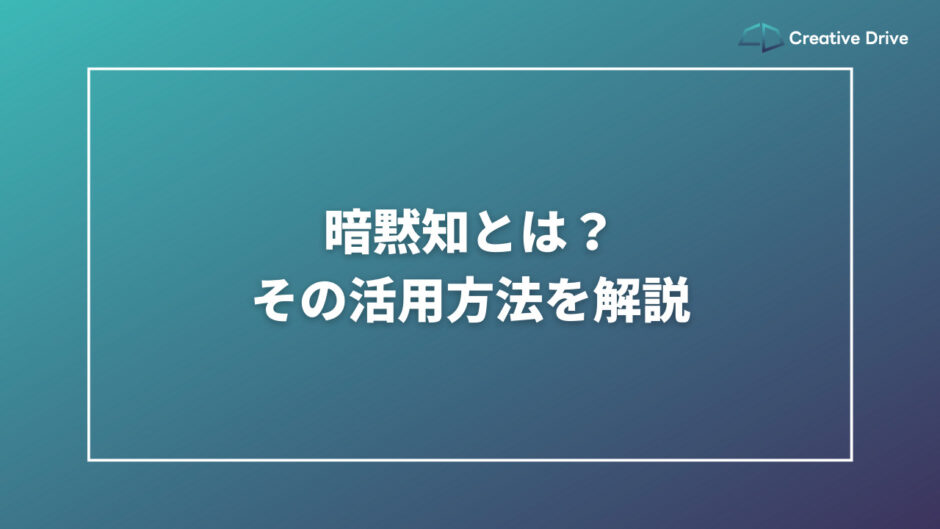
我々が日々過ごす中で、言葉にはしないが自然と身についた知識があります。それが「暗黙知」です。具体的な暗黙知とは何なのか、それがどのように生まれ、どのように活用されるのか。また、暗黙知の特性や種類、獲得方法から、活用のコツや注意点まで幅広く解説していきます。自分自身の暗黙知に気づき、それを上手に活用することで、ビジネスや学問、スポーツなど、さまざまな場面で大きな結果を生むことが可能となります。知識管理という視点からも暗黙知は重要な存在であり、その活用法を理解し実践していくことが求められます。







Meeting, planning or hands on documents for tax audit report or financial statement in company. Accounting, business people or closeup of strategy for finance paperwork, logistics or data analysis.
目次
暗黙知の定義

知識管理の中の暗黙知とは
知識管理とは、企業の競争力を左右する一因となる「知識」を最適に活用するための取組みのことを指し、その中でも暗黙知は非常に重要な位置を占めています。なぜなら、暗黙知は個々の経験や感覚に基づくものであり、他人に伝えることが難しいため、一度失われると二度と戻らない大切な知識だからです。例えば、ある作業を何年も行い続けてきたベテランのスタッフがいるとします。彼らが持つノウハウや経験は、新人が追いつくには何年もの時間を要するものですが、このような知識や経験は暗黙知となります。こうした暗黙知を可視化し、組織全体で共有することで生産性の向上や効率化が図られます。明示知と暗黙知の違い
明示知とは、文章や図表、数学的な式など、形式的な方法で表現した文字や記号などによって表現可能な「明示的な」知識を指します。一方で、暗黙知は主観的な洞察力や直感、仮説を形成する能力など、他の人と共有しにくい、一人ひとりの心の中で経験や学びを通じて蓄積される知識を指します。例えば、自転車の乗り方を教えるとき、ペダルをこぐ技術やバランス感覚などは、暗黙知に分類され、教科書やマニュアルには残せない情報となります。このように、明示知と暗黙知は明確に区別され、それぞれの知識が持つ役割や活用方法も異なります。暗黙知の特性
暗黙知は複雑で主観的な特性を持ち、人間の行動や意思決定に影響を与える、個々に特有のノウハウや経験、感覚、価値観を含むため、明示知とは異なり、言葉による説明が困難であり、具体的には何に使えるかを想像しにくいという特性があります。また、その形成過程が特定の文脈や状況に縛られるため、その知識を抽出し、他の人へ伝達することは非常に難しい課題となります。しかし、暗黙知はその独自性が組織や個人の競争優位性を生み出す源泉でもあります。これが暗黙知を理解し活用することが企業にとって重要な意味を持つ理由となります。暗黙知の種類

感覚と経験に基づく暗黙知
感覚と経験に基づく暗黙知は、個々人がその経験から得た知識や感覚の総体です。これは具体的な行動や判断、思考に影響を与える強力な知識源であります。例えば、似たような状況を何度も経験したことで、必要な行動や選択肢が直感的にわかるというようなものです。これは、具体的で繰り返しの経験から得られる知識であり、それが行動や判断に影響を与える力強いインプットとなるのです。この種類の暗黙知を活用するためには、経験を通じて得られる知識を丁寧に吟味し、それを活用できるフレームワークを作り出すことが大切です。本能と直感に根ざす暗黙知
本能と直感に根ざす暗黙知は、感情や直感、本能から生まれる知識のことを指します。これは、理論的に説明することが難しい、あるいは不可能な知識であり、人間の感情や直観的な部分、本能的な部分から生まれます。これは、自然な反応や行動を通じて現れることが多く、その知識を活用することで高度な問題解決能力や課題を進行させる力、人々との良好な関係を築くことが可能になります。この種類の暗黙知を活用するためには、心の声を聞くことや自己理解を深めることが必要となります。技術やノウハウに関する暗黙知
技術やノウハウに関する暗黙知は、その名の通り特定の技術やノウハウに関する知識です。これは、特定の戦略やテクニック、方法、手順などの進め方や扱い方、使い方などの具体的な知識を指します。この種類の暗黙知は、それを実際に行ってみなければ理解できないことが多いのが特徴で、それを活用するためには、具体的な行動や実践が必要となります。この暗黙知を効果的に活用するためには、実際の操作を通じた体験や、指導者からの直接の教えが大切となります。暗黙知の獲得方法

体験を通した暗黙知の獲得
「体験を通じて学ぶ」とは、具体的な経験を通じて得られる知識のことを言います。この方法は、暗黙知の獲得にとって非常に重要な一つです。何故なら、体験を通じて身につけた知識やスキルは、頭で理解するだけでは得ることが難しい深い理解が可能となるからです。例えば、外国語を学ぶ場合、単に辞書で単語や文法を覚えるだけではなく、実際にその国に行き、その言語を使用することで、自然と暗黙知として身につけていくことが可能になります。このように、体験を通じた暗黙知の獲得は、実践的で豊かな理解を可能にします。学習から得る暗黙知
学習から得る暗黙知とは、一般的には教育や訓練、練習を通じて得られる知識やスキルのことを指します。この方法は、特定のスキルやノウハウを身につける場面において非常に効果的です。例えば、楽器を習う場合や新しいプログラミング言語を学ぶ場合などです。一定の時間と労力をかけて一つひとつの知識やスキルを身につけることで、それらが暗黙知として身についていきます。また、この方法は、自分の成長を可視化し、具体的な目標設定や計画を立てることが可能なのも大きな魅力と言えます。コミュニケーションによる暗黙知の獲得
暗黙知を獲得するもう一つの重要な方法が、コミュニケーションを介した方法です。これは、他人との対話や交流を通じて、その人が持つ知識や経験、感覚などを吸収する方法を指します。特に、先輩やメンターからの直接的な指導やアドバイスは、これらの知識や感覚を共有し、自分自身の知識として身につける上で非常に有効です。また、ディスカッションやブレインストーミングによっても、他人の視点やアイデアを聞くことで新たな知識や視点を得ることが可能となります。コミュニケーションによる暗黙知の獲得は、協働や共創による成果を生む上で欠かせない方法です。暗黙知の共有

コミュニケーションによる暗黙知の共有
暗黙知の共有方法の一つとして、「コミュニケーション」があります。暗黙知は言葉では表現しきれない知識ですが、それを言葉や行動によって他者に伝えることで共有することが可能となります。日常的な会話やディスカッション、振り返りの時間などを通じて専門知識やノウハウ、経験や感覚などを共有することが大切です。しかし、暗黙知の共有は、発信者が自己の知識や経験を自覚し、それをどう伝えるかという技術が問われます。また、受信者側も暗黙知を理解し吸収するための理解力や共感力が重要となります。したがって、コミュニケーションによる暗黙知の共有は意識的な取り組みが求められます。知識管理システムと暗黙知の共有
次に、技術的な方法として、「知識管理システム」による暗黙知の共有が挙げられます。知識管理システムは、組織内の知識を一元管理し、必要な情報を効率良く検索・共有できるツールです。暗黙知を共有するためには、それを文書化し、体系化することが必要です。その点、知識管理システムは文書化された知識を管理・活用するための枠組みを提供し、効率的な情報共有を可能にします。具体的な方法としては、プロジェクトや問題解決の経緯を記録し、それを他のメンバーが参照できるようにする方法などがあります。社内教育と暗黙知の共有
最後に、「社内教育」による暗黙知の共有について解説します。社内教育は、オンボーディングの段階から始まり、組織内の成長と共に進化し続けるべきプロセスです。暗黙知を活用した社内教育では、例えば、ミーティングやワークショップ、研修などを通じて先輩社員から新入社員へ知識や技術、経験を伝えることが可能です。また、ロールプレイやシミュレーションを行うことで、具体的な状況や問題を想定して解決策を考える力を養うことも可能です。これらの教育活動を通じて、組織全体での暗黙知の共有と活用が進みます。暗黙知の活用事例

企業における暗黙知の活用
企業の中では、暗黙知の活用は日常的に行われています。訓練や教育プログラムの一部として、従業員が具体的な業務に対してどのように意識したり行動するかを学び、その経験を他の仕事にも生かすことが求められます。これは、暗黙のうちに身につけた技術や手法を他者に伝達し、組織全体の業績向上に寄与するという意味で、暗黙知の活用の一例です。企業内での暗黙知の活用は、個々のスキルや能力を最大限に引き出し、組織全体の競争力を高める効果があるのです。学術研究における暗黙知の活用
学術研究においても暗黙知は大変重要な役割を果たしています。研究者は、自分自身の感覚や経験を通じて得た知識を活用し、新しい知識を創出しています。特に実験の現場では、他の研究者が起こりうる意外な結果に対応するための技術や手段として暗黙知が活用されます。また、学術的な論文や報告書では表現できない微妙な感覚や視点が、学者間で口頭や非公式のチャンネルを通じて共有されています。これらの情報交換もまた、暗黙知の活用例と言えるでしょう。スポーツ界における暗黙知の活用
スポーツ界でも暗黙知の活用は一般的です。具体的な技術の習得だけでなく、ゲームの流れを読む力や、瞬間的な状況判断力といったものがそれに該当します。これらの能力は何度も練習を重ねることで身につけられ、言葉で説明することが難しいものの、結果としてスポーツパフォーマンス向上に繋がります。暗黙知の活用が不可欠なのは、このような高度な技術や判断力を養うプロのスポーツ選手だけでなく、初心者が新たなスポーツを学ぶ際にも同様です。活用方法とそのデメリット

暗黙知活用の際の注意点
暗黙知を活用する際には、まずその特性を理解することが大切です。暗黙知は明示知と違い、形式化するのが困難で言葉で表現しにくい知識であるという性質を持っています。そのため、共有する際には実際の現場に立って体験する、または具体的な事例を通じて理解することが求められます。また、暗黙知は特定の人間に独特の知識や経験に基づくため、他の人にそのまま移すことは難しいです。したがって、その暗黙知を持っている人がいつまでもその知識を持ち続け、それが企業全体に広まらないという状況を防ぐためにも、適切なメンタリングやコーチングを行うことが重要です。暗黙知の活用におけるデメリット
暗黙知の活用には多くのメリットがある一方で、そのデメリットも理解しておかなければなりません。ひとつ目のデメリットは時間とコストです。暗黙知を共有するためには、実際に現場に立って実践するだけでなく、専門家からの指導や体験を通じて学び取る時間が必要です。しかし、この時間とコストは無視できないもので、全てのスタッフに平等に暗黙知を共有するのは非現実的とも言えます。二つ目のデメリットは、誤解や混乱を招く可能性があることです。人によっては同じ暗黙知でも理解や解釈が異なるため、それがビジネスの混乱を招く可能性があります。暗黙知と法的問題
暗黙知の活用には法的な問題も伴います。特に技術や特許に関する暗黙知は、その利用方針が法律に違反する可能性があります。また、その暗黙知が企業のコンピテンシーや秘密情報に当たる場合、不適切な共有や流出は企業の競争力に直接影響を及ぼす危険性があります。したがって、暗黙知の活用はしっかりとルールを設け、従業員にその遵守を徹底させることが求められます。一方、それらを適切に管理し、暗黙知を活用することで、企業は独自の競争力をつくることができるでしょう。暗黙知の実践的活用方法