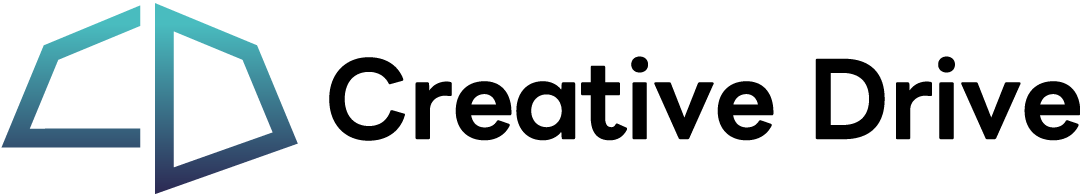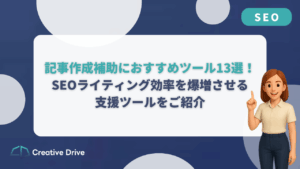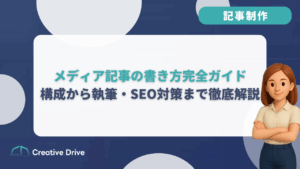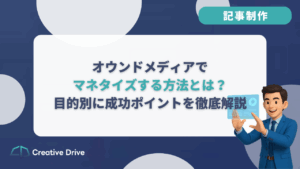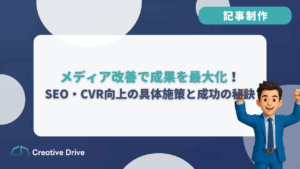オウンドメディアを外注するメリットと業務範囲|成功する外注活用法を徹底解説
2025年09月01日

オウンドメディアは、自社の認知拡大やリード獲得、採用ブランディングなど幅広い目的に活用される重要なマーケティング施策です。しかし、戦略立案から記事制作、SEO対策、進行管理、さらには効果測定まで、多くの工程が必要となり、自社だけで運用を完結させるのは容易ではありません。そこで注目されているのが「外注」の活用です。専門性の高い領域を外部パートナーに任せることで、効率化と成果の両立を実現できます。
本記事では、オウンドメディアの依頼を外注するメリットや注意点を紹介。また、外注可能な業務の種類や外注先の選び方も詳しく解説します。
目次
オウンドメディア運用は外注がおすすめ

オウンドメディアの運用は、自社だけで完結させるのが難しい業務のひとつです。記事執筆や構成設計、編集、画像制作、さらには運用管理に至るまで、幅広い工程を外注できる点が大きな特徴です。
特に、SEOに最適化された記事を継続的に発信するには相応の知識とリソースが必要であり、社内のリソースだけでは限界が出やすいものです。そのため、必要な部分を外部に委託することで、効率よく高品質なコンテンツを蓄積し、成果を最大化できます。
オウンドメディア運用を外注するメリット

オウンドメディア運用を外注するメリットは、大きく分けて以下の3点です。
・品質の高いコンテンツ制作が可能になる
・継続的な発信でスピード感を持った成長を実現できる
・内製化と両立し、自社にノウハウを蓄積できる
次に、具体的な3つの観点からオウンドメディア運用を外注するメリットをみていきましょう。
メディアの品質を担保できる
オウンドメディアの運用を外注する最大の魅力は、専門的な知識を持つライターやSEOコンサルタントを活用できる点です。記事制作を社内の担当者だけで行う場合、業界知識はあってもSEOの視点が弱い、あるいは文章力にバラつきがあるといった課題が生じやすくなります。その結果、記事の質が安定せず、検索順位や流入数の伸び悩みにつながる可能性があります。
オウンドメディア運用を行う業者に外注すると、リサーチ力の高いライターや編集者のサポートによって、検索エンジンに最適化された記事を制作可能です。特に競合が多い領域では、検索ユーザーの意図を的確に捉えた高品質な記事が成果の分かれ道。外注を活用することで、記事の品質を安定させ、ブランド価値を損なわずに継続的な集客が可能になります。
スピード感を持ったメディア成長を目指せる
オウンドメディアを成功させるには、記事の「質」と「継続性」の両方が欠かせません。検索エンジンは一定のペースで更新されるサイトを評価する傾向があり、長期的にアクセス増加につながります。ただし、量を優先して質の低い記事を量産すると逆効果になる可能性があるため注意が必要です。
外注を活用すれば、必要なタイミングで必要な分だけリソースを確保できるため、社内の負担を抑えながら高品質な記事を安定的に公開できます。特に新規立ち上げ期には、一定数の記事を短期間で整備することが重要であり、外注の力を借りることでスムーズに基盤を築けます。
結果として、「質を担保しつつ継続的に更新する体制」を早期に整えられるため、成長スピードを落とさず効率的に規模を拡大できるでしょう。
内製化支援が受けられる
外注は専門性とスピードを活用できる反面、自社にノウハウが蓄積しにくい課題もあります。そこで一部の業者では「外注しながら内製化を支援する」サービスを提供しています。
この仕組みを利用すると、記事制作や編集を外注しつつ、社内担当者がディレクションやSEOの基本を学ぶ機会を得ることが可能です。中長期的には自走できる体制を築きやすくなるため、短期的な成果と社内ナレッジの蓄積を両立できます。また「戦略は社内、制作や校正など工数の大きい部分は外注」といったハーフ内製を選択することで、持続的な成長につながりやすくなります。
オウンドメディア運用を外注する注意点

オウンドメディア運用の外注は、効率化や品質向上に大きな効果をもたらす一方で、注意すべき課題も存在します。成功する外注活用のためには、発注前に準備を整え、明確な指示や基準を提示することが欠かせません。ここでは、外注時に気をつけるべき3つの注意点を詳しく解説します。
コストがかかる
オウンドメディアを外注する際に最も気になるのがコストです。外注費用は記事の長さや専門性で変動しますが、一般的には1本あたり数千円〜数十万円程度が目安となります。月に複数本を依頼すると、数十万円規模の出費になるケースもあるでしょう。
短期的には大きな負担に感じられるかもしれませんが、質の高い記事は公開後も検索流入を生みやすく、中長期的には「資産」となり得ます。ただし、検索順位はGoogleのアルゴリズム変更や競合の動向によって変動する可能性があるため、必ずしも効果が安定して続くわけではありません。そのため、定期的なリライトや改善を見据えた運用が必要です。
コストを抑えたい場合は、まずは記事執筆のみを外注し、戦略や構成設計は社内で担う“部分外注”から始めるのがおすすめです。これにより、費用を抑えつつ効果を実感しやすくなります。
認識のズレが起こる可能性がある
オウンドメディア運用の外注で頻発しやすい失敗が「イメージと違う記事が納品された」というケースです。原因の多くは、発注側と受注側の認識のズレにあります。たとえば「読者層の解釈」「記事のトーン」「目的とする成果」などを共有しないまま進めると、完成した記事が自社の意図に合わないものになる可能性が高まります。
認識のズレを防ぐには、発注前に「ペルソナ」「記事のトーン&マナー」「参考記事」を整理した指示書を準備することが不可欠です。さらに納品後もフィードバックを重ね、改善点を明確に伝えることで、徐々に期待値に近づけることができます。外注は丸投げではなく、パートナーと一緒に作り上げていく「伴走型」の姿勢が成功のカギになります。
記事のクオリティにバラつきが出る場合がある
複数の外注先を活用する場合、記事ごとの品質に差が出る可能性もあります。ある記事はリサーチが深く読み応えがある一方で、別の記事は浅く表面的な内容にとどまってしまうこともあります。また、誤字脱字や言い回しの不統一など、細かい部分でのクオリティ差も発生しやすいのが実情です。
記事のバラつきを防ぐには、編集者や校正者を外注チームに組み込み、全体の品質を均一化する仕組みを整えることが重要です。ガイドラインを策定してトーンや表現ルールを統一すれば、ブランドとしての一貫性も維持できます。記事制作を単発で依頼するよりも、ライターと編集者をセットで外注する体制を構築すると、安定的に高品質な記事を公開できるようになります。
オウンドメディアの外注ができる業務の種類

オウンドメディアを外注する際、「記事執筆」だけを委託できると考える方も多いですが、実際には幅広い業務を外部に任せることができます。企画や構成案の立案、記事執筆や編集作業に加え、デザインや画像制作、運用や進行管理まで委託可能です。これらを自社の強みやリソースと照らし合わせながら組み合わせることで、より効率的かつ成果につながる運用体制を築けます。ここからは、代表的な外注業務の種類を詳しく紹介します。
記事執筆・ライティング
最も多くの企業が外注している業務が「記事執筆」です。SEO記事では検索ボリュームのあるキーワードを狙いながら、ユーザーの検索意図を正しく汲み取り、課題解決につながる文章に仕上げることが求められます。記事執筆を社内で完結させると、専門知識はあってもSEOに最適化されていなかったり、逆にSEOに強くても業界理解が浅かったりといった課題が生じやすいのが実情です。
外注先に依頼すれば、SEOリサーチと記事執筆をセットで対応できるため、検索上位を狙いやすくなります。また、複数のライターを抱える業者に依頼すれば記事の量産も可能になり、短期間でオウンドメディアの規模を拡大できる点も魅力です。特にBtoB領域や医療、不動産など専門性が高い分野では、専門知識を持つライターとSEOディレクターの組み合わせで依頼するのがおすすめです。
構成案・企画立案
記事の出来栄えを左右するのが「構成案」です。どのキーワードを狙うのか、どのような見出し構成にするのか、どんな読者の悩みを解決するのかといった要素を整理することで、記事の質は大きく変わります。構成案を自社で作る場合、どうしても担当者の経験や知識に依存してしまいがちですが、外注であればSEOコンサルタントや編集者が競合分析・検索意図分析を踏まえて論理的に構成を設計してくれます。
また、検索エンジンから評価されやすい記事を効率的に作れるだけでなく、ライターが迷わずに執筆できるため、納品後の修正工数を減らせる効果も期待できるでしょう。記事制作を外注する場合は、ライティングとあわせて構成案づくりを依頼すると品質が安定しやすくなります。
編集・校正
複数のライターが関わるオウンドメディア運用において、品質を均一に保つのは容易ではありません。誤字脱字のチェックはもちろん、表現の統一やトーン&マナーの統制、SEO観点での不足点の補完など、編集・校正業務は非常に重要です。外注することで、プロの編集者が記事全体のクオリティを底上げし、ブランドとしての一貫性を担保できます。
特に記事数が増えてきたフェーズでは、編集者の有無で記事の完成度に大きな差が出ます。記事を単発で依頼するよりも、編集者をチームに組み込むことで「納品記事をそのまま公開できる」状態に近づけやすくなるのがポイント。記事制作の品質を長期的に高めたい場合、ライターと編集者をセットで外注する体制も有効です。
デザイン・画像制作
テキストだけの記事は情報量としては十分でも、読者にとって理解しづらいことがあります。「デザイン」や「画像制作」を外注すると、アイキャッチ画像を工夫するだけでクリック率が改善が可能になる場合があります。また、記事内に図解やインフォグラフィックを挿入することで、専門的な内容でも直感的に理解しやすくなるのもポイントです。
BtoBの事例記事やノウハウ記事では、文章だけよりも図表を交えた方が説得力が増し、読者の滞在時間やシェア率の向上に直結します。外注先に依頼する際は、記事のトーンやブランドカラーに沿ったデザインを指定すると、サイト全体の統一感も高められます。
運用・進行管理
オウンドメディア運用は、記事を作るだけでなく「継続的に更新し続ける」ことも成果に直結します。しかし実務的には、ライターとのやり取り、納期管理、校正の進捗確認、公開作業、分析・改善提案といった業務が発生するのが実情。担当者に大きな負荷がかかる可能性もあります。
「進行管理」を外注すると、社内は戦略や方向性の策定に集中できるようになります。外注先によっては、記事公開後のアクセス解析や改善提案まで一括で請け負ってくれる場合もあり、制作代行にとどまらず運用パートナーとして伴走してくれるのが強みです。中長期的にメディアを成長させたい企業にとっても、運用・進行管理の外注は非常に有効な選択肢となるでしょう。
オウンドメディアで成功するための外注先の選び方

オウンドメディア運用の外注は、記事を納品してもらうだけではなく、成果につながるパートナー選びが重要です。ここでは、外注先を選定する際に必ずチェックしたいポイントを3つ紹介します。
実績が豊富な業者・ライターを選ぶ
外注先を選ぶ際は、実績を確認するのがおすすめです。記事制作の経験があるだけではなく、SEOで検索上位を獲得した事例や、オウンドメディアを通じて流入数やリード獲得数を伸ばした成功事例を持っているかを確認しましょう。実績が豊富な業者やライターは、ただ記事を納品するのではなく、成果につながるためのノウハウを体系化している場合もあります。短期間で期待値に近い効果を得やすくなるでしょう。
また過去のクライアントや業界を確認することで、自社の分野に対応可能かどうかも判断できます。単なる「制作代行」ではなく「成果創出」の実績を持つパートナーを選ぶことが成功への近道です。
リサーチ力と構成設計力のある業者・ライターを選ぶ
オウンドメディアの記事品質は、ライターの文章力だけで決まるものではありません。鍵を握るのは「リサーチ力」と「構成設計力」です。検索ユーザーが求める情報を的確に抽出し、競合記事を分析したうえで、論理的に整理された構成を作れるかどうかで記事の完成度が大きく変わります。リサーチ力が弱いと情報の網羅性に欠け、SEO的に評価されにくい記事になってしまうでしょう。
また、構成設計が甘いとライターが執筆しづらく、納品後の修正作業も増えやすくなります。発注前に外注先の過去記事やサンプル構成案を確認し、検索意図の分析ができているか、読者の課題解決につながる構成を作れているかをチェックするのがおすすめです。
柔軟性のある業者・ライターを選ぶ
外注先を選ぶ際には、柔軟に対応できるかどうかも重要な判断基準です。完全に外注に任せる方法もありますが、長期的に成果を安定させるには「戦略部分は社内で担い、記事制作や編集といった工数の大きい業務を外注する」というハーフ内製もおすすめです。ハーフ内製に適応できる外注先は、依頼内容に合わせて柔軟に業務範囲を調整してくれるため、社内リソースの状況に応じて最適な協力体制を組むことができます。
また、運用の初期は全面的に支援してもらい、軌道に乗ってからは社内への引き継ぎをサポートしてくれる業者であれば、ノウハウを社内に蓄積しながら成果を上げられます。柔軟性を持つパートナーを選ぶと、持続的なメディア成長にも直結しやすくなるでしょう。
オウンドメディア運用を外注する前に決める3つのこと

オウンドメディア運用は、記事制作や運営を委託するだけでは十分な成果を得られない場合があります。大切なのは「どのような体制で外注し、どの流れで進めるのか」を明確に定めておくことです。発注内容や役割分担があいまいだと、不要なやり取りが増えたり、期待した成果からズレたりするリスクが高まります。
ここでは、外注を成功させるために必ず準備しておきたい3つのポイントを解説します。
読者像(ペルソナ)を決める
オウンドメディアを成功させるうえで欠かせないのが「誰に読んでもらうか」を明確にすることです。読者像が曖昧なまま記事を制作すると、内容が広く浅くなり、ターゲットに響かない記事になりがちです。外注先に依頼する際も、ペルソナが定義されていなければ「記事の方向性がずれる」「想定していない読者層に届いてしまう」といった失敗につながります。
年齢や職業、抱えている課題、情報収集の目的など、具体的な人物像を事前に共有しておくことで、ライターや編集者もターゲットに即した記事を作りやすくなります。ペルソナ設計は記事のトーン、構成、事例選びなど全体に影響するため、外注前に必ず設定しておきましょう。ペルソナの設定方法がわからない場合は、立ち上げからサポートを行う業者に依頼するのもおすすめです。
目的を決める
オウンドメディアを外注する際には「何のためにメディアを運営するのか」という目的を明確にすることが不可欠です。認知度向上やリード獲得、採用強化、ブランディングなど、目的によって制作すべき記事のテーマや評価指標は大きく変わります。
たとえば、リード獲得が目的ならSEOを意識した課題解決型の記事が効果的ですが、採用を目的とするなら社風や社員インタビューを紹介するコンテンツが必要になります。目的が曖昧なまま外注すると、記事の内容が分散し、成果に直結しにくくなるでしょう。外注先に目的を明確に伝えることで、戦略やKPIを共有しやすくなり、依頼内容も的確に定められます。結果として、投資対効果を最大化することが可能になります。
依頼する範囲を決める
外注を効果的に活用するためには、どこまでを外部に委託し、どこを自社で担うのかを明確にする必要があります。記事執筆のみを依頼するのか、構成案や編集、さらには運用・進行管理まで含めるのかで、外注費用や運営フローも大きく変わります。
範囲を曖昧にしたまま依頼すると「思ったより社内の負担が減らない」「逆に想定以上のコストがかかった」といったトラブルが起こりがちです。自社の強みや社内リソースを踏まえて、戦略部分は社内、制作や管理業務は外注といった役割分担を決めておくことが理想です。外注先にもその方針を明確に伝えれば、無駄のない体制を構築でき、長期的に成果を上げやすくなります。
まとめ
オウンドメディアの外注は、記事執筆から構成案の設計、編集、進行管理に至るまで幅広く委託できるのが特徴です。効率的に高品質なコンテンツを積み上げられる一方で、コストや認識のズレといったリスクも伴うため、外注先の選定や発注設計が成果を左右します。大切なのは、自社の体制や目的を明確にしたうえで、必要なサポートを提供できる外注先を選ぶこと。信頼できるパートナーを見つければ、効率的かつ成果につながるオウンドメディア運用が実現できるでしょう。
Creative Driveでは、豊富な実績を持つライター陣が在籍しており、専門性の高い領域でも確かなリサーチと論理的な構成設計で成果につながる記事を制作します。記事執筆だけでなく編集や進行管理、運用改善の提案まで幅広くサポート可能です。単なる制作代行にとどまらず、伴走型のパートナーとしてお客様のオウンドメディア成長を支援しています。
・「どこまでを外注すべきか迷っている」
・「高品質な記事を安定的に制作したい」
・「社内リソースを最適化しながら成果を出したい」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度Creative Driveへご相談ください。あなたのオウンドメディア運用をサポートします。