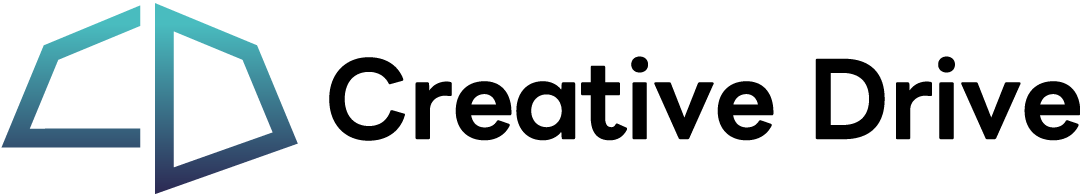オウンドメディア記事の書き方完全ガイド|構成から執筆・SEO対策まで徹底解説
2025年09月01日
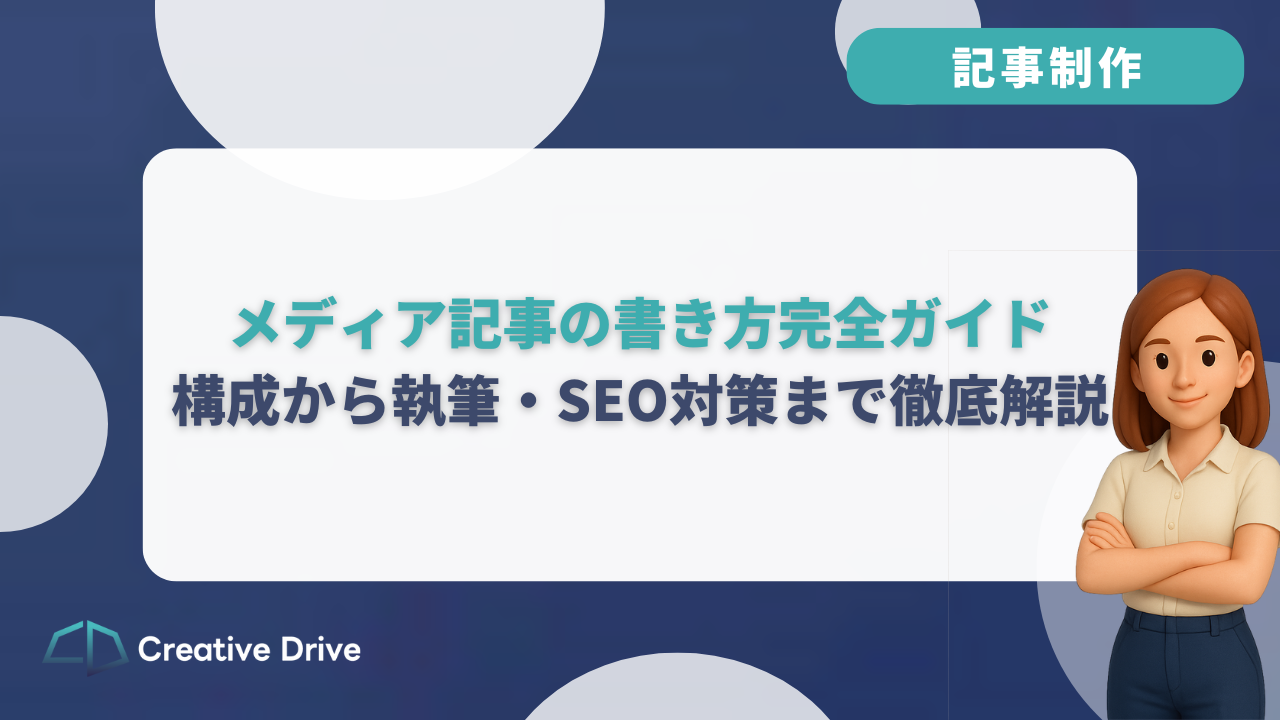
オウンドメディアは、自社のブランディングや集客を目的に「自社で情報発信するメディア」として近年注目されています。しかし「記事の書き方がわからない」「SEOを意識した構成が作れない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、オウンドメディアの記事制作に必要なキーワード選定・構成案作成・SEOライティングのコツ・リライト戦略までを徹底解説します。これから記事制作を始める方も、既に運用中で改善を目指す方も、実務に活かせる内容となっています。
目次
オウンドメディア記事とは?

オウンドメディア記事は、企業のマーケティング活動において単なる情報発信を超えた重要な役割を担っています。自社が所有するメディア全般を指し、そのコンテンツとしてブログ記事やコラム、ホワイトペーパー、事例紹介ページなどが含まれます。
その強みは、自社の裁量で情報を発信できる点です。SNSや広告媒体はプラットフォームのルールに依存するのが特徴。一方、オウンドメディアは検索流入による安定したアクセスを見込める資産です。時間をかけてコンテンツを蓄積すると、広告コストに頼らない集客基盤となり、長期的に企業の信頼性やブランド力を高めることができます。
オウンドメディアで記事を書く3つの目的

オウンドメディアで記事を書く目的は、大きくわけて以下3つに整理できます。
・検索からの集客
・読者との信頼構築
・ブランディング
記事を通じて潜在顧客を呼び込むことで、サービスや商品の検討につなげます。課題を解決する有益な情報を提供すれば、企業に対する安心感も生まれるでしょう。さらに、専門的な知見を継続的に発信することで業界内での権威性を高め、「この分野といえばこの会社」というポジションを確立。広告と違い、読者に役立つ情報を軸にした自然な接点づくりができるのが魅力です。
書き手が心がける基本スタンスは?
オウンドメディア記事を執筆する際は「ユーザーファースト」の姿勢を徹底することが欠かせません。企業の都合を優先した一方的な発信をすると、読者の信頼を失う原因になる場合があります。検索ユーザーは「自分の悩みを解決できる記事」を探しているため、その期待に応える情報設計が必要です。
また記事は自社商品の宣伝の場ではなく、読者の課題解決を支援する場として設計するのもポイント。リサーチを丁寧に行い、検索意図を的確に捉えて内容を作ると、結果的にSEO評価も高まって自社への信頼やブランド価値向上につながります。
オウンドメディアを成功させるための準備

オウンドメディアを成功させるためには「どのキーワードで勝負するか」「誰に向けて書くか」を明確にすることが不可欠です。ここでは、オウンドメディアを成功させるために必要な準備であるキーワード選定の考え方と、読者像を定義するペルソナ設計の重要性について解説します。
SEO視点でキーワードを選ぶ
記事執筆は、はじめに検索ニーズを反映したキーワード選びを行うのがポイントです。検索ボリュームが大きすぎると競合が強く、上位表示が困難になります。一方で、ニッチすぎると流入が見込めません。適度なボリュームと競合度を見極めることが重要です。
Googleキーワードプランナーやラッコキーワードを用いて候補を収集し、検索意図を分析しましょう。たとえば「オウンドメディア 書き方」で検索するユーザーは、執筆の具体的な手順やSEOのコツを求めています。検索意図を理解し、記事全体の構成に反映させると、検索流入と読者満足度の両立が可能になります。
ペルソナを設定する
記事の方向性を明確にするためには、「想定読者=ペルソナ」を設定することが重要です。ペルソナは年齢・職業・課題・情報収集方法などを細かく定義します。
たとえば「中小企業のマーケティング担当者・30代・SEO初心者」を想定すると、記事は基礎的な知識から実践方法まで丁寧な説明が必要です。逆に「大手企業のマーケティング部長」を対象にする場合、業界動向や戦略的な施策の話が中心になるでしょう。
誰に語りかける記事なのかを具体化すると、文章のトーンや情報の深さを適切に調整でき、読者に強く響く記事が完成します。
オウンドメディア向けの記事構成の作り方
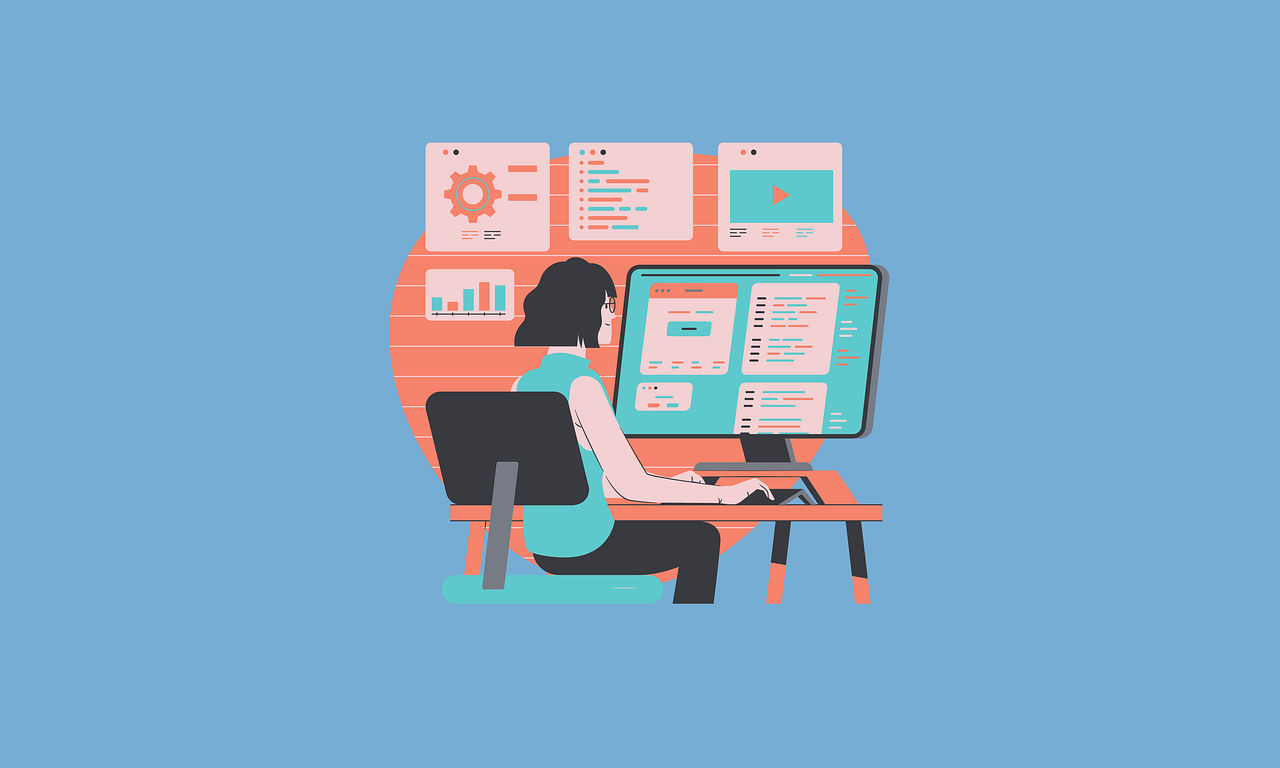
良質な記事は、書き始める前の「構成設計」でほぼ決まります。検索意図を網羅するために、h2・h3を使って論理的に情報を整理することが必要です。ここでは構成案作成の流れや見出し設計の工夫を紹介します。
構成案の作り方と全体設計の考え方を理解する
記事の構成案は、以下のような流れを意識して作るのが基本です。
①結論
②理由
③具体例
まず読者の検索意図に対する答えを明示し、その根拠や背景を説明し、最後に具体例や手順を提示することで説得力が増します。記事を書き始める前に見出しレベルで骨組みを作ることで、論点が散らからず、最後まで一貫性のある記事になります。また、全体設計を事前に固めると、複数ライターで分担しても品質を保ちやすくなるのもメリットです。記事の完成度は、この構成設計にかかっているといっても過言ではありません。
結論ファーストでPREP法を活用する
検索ユーザーは「早く答えを知りたい」と考えているため、記事では結論ファーストを意識することが重要です。その際に有効なのがPREP法(Point・Reason・Example・Point(まとめ))です。最初に結論を示して理由を述べ、具体例を提示し、最後に再び結論をまとめるという流れは、情報をわかりやすく伝える王道の構成です。
特にビジネス系の記事では説得力が増し、読者の理解が深まりやすいでしょう。結論を最後まで引っ張るよりも、冒頭で示した方が読了率も高まり、SEO評価にもつながります。
見出しに数字やメリットを入れてクリック率向上を狙う
検索結果で目を引く記事タイトルや見出しには、数字やメリットを盛り込むのが効果的です。たとえば「5つの方法」「3ステップで解決」などの表現は、読者に「短時間で理解できそう」と思わせ、クリック率向上につながります。
さらに見出しにメリットを含めると、記事全体の読み進め率も上がります。SEOではクリック率も重要な評価指標の一つであるため、タイトルや見出しの設計は記事の成果を左右する重要なポイントです。具体的な数字やベネフィットを入れる工夫を積極的に取り入れましょう。
SEO評価が上がりやすい記事の書き方の基本

オウンドメディアの記事制作で最も重要なのは「検索意図に沿ったコンテンツを提供すること」です。検索ユーザーは「自分の疑問や課題を解決したい」という目的を持って記事を探しています。ユーザーの期待に応えられない内容の記事は、すぐに離脱されてしまいSEO評価も下がりやすいでしょう。検索意図は以下のように大きく3段階に分けられます。
・ナビゲーショナル(navigational):特定のサイトに行きたい
・インフォメーショナル(informational):情報を知りたい
・トランザクショナル(transactional):購入や行動をしたい
記事のテーマごとに、読者がどの段階で検索しているのかを見極め、それに合わせて情報の深さや具体性を調整することが大切です。
たとえば「オウンドメディア 書き方」で検索するユーザーは、「基本的な手順や構成方法を知りたい」という情報収集段階にいると考えられます。したがって、基礎的な説明や具体的な執筆フローを提示する記事が適切です。ここで「制作代行サービスの紹介」だけを行ってしまうと、読者の期待とずれて離脱されやすくなります。検索意図を正しく把握し、それに応える記事を作ることが、ユーザー満足度とSEO評価を両立させる最大のポイントです。
視認性向上につながる執筆時の3つのポイント

オウンドメディアの記事は、SEO観点で書くだけではユーザー獲得につながるとは限りません。文章のわかりやすさやレイアウトによっても評価が大きく変わります。続いては、視認性向上につながる執筆時のポイントを3つみていきましょう。
1.わかりやすい文章を書く
文章は、シンプルかつ平易であるほど伝わりやすくなります。SEO記事においては特に「専門用語を補足する」「長文は短く分ける」「一文一意を徹底する」ことが重要です。また、文字だけでは伝わりにくい内容は図や表を活用することで理解度を高められます。
特にBtoB領域ではフローチャートやプロセス図を交えると、読者が自分の業務に照らしてイメージしやすくなります。シンプルにまとめつつも、必要に応じてビジュアルを取り入れることが、わかりやすい記事執筆のコツです。
2.強調表現で視認性を改善する
読者が記事を読み進めるなかで「重要なポイントがひと目でわかる」ことは、読了率を高めるために欠かせません。そこで効果的なのが強調表現の活用です。
太字やハイライトで重要語句を目立たせれば、読者は流し読みでも大事な内容をキャッチできます。ただし強調の多用は逆効果になる場合もあるでしょう。全体のなかでメリハリを付けて、要所にだけ強調を使うことがポイントです。見出し・段落構成と併せて調整すると、記事全体の視認性が飛躍的に向上します。
3.リスト・段落・サブヘッダーで読みやすくする
長文になりやすいSEO記事では、リストや段落分けを駆使して「視覚的に整理された文章」を意識する必要があります。ユーザーは画面をスクロールしながら「自分に必要な情報」を探しています。
そのため、長文をだらだら続けるよりも、箇条書きや表を挟むことで可読性が向上。また、適度にサブヘッダー(h3以下)を追加すると、読者が途中からでも目的の箇所を見つけやすくなるでしょう。結果的に直帰率が下がり、SEOにも良い影響を与えることにつながります。
オウンドメディアの公開前チェックに行うSEO対策

記事を公開する前は、SEO観点で最終チェックを行うことが不可欠です。タイトルや見出しへのキーワード配置はもちろん、サイト全体の内部SEO施策とも連携させて精度を高めましょう。最後の確認で差が出る場合もあります。ここからは、SEO対策としての構成とオウンドメディアに公開する前に行っておきたいポイントを解説します。
タイトルと見出しへのキーワード配置を最適化する
SEOで最も影響が大きいのは記事タイトルです。メインキーワードは冒頭に配置するのがおすすめです。見出し(h2・h3)にも自然にキーワードを組み込むと、検索エンジンに記事のテーマを明確に伝えられます。
ただし無理に詰め込みすぎると可読性を損なうため、自然な文脈に溶け込ませることが大切。記事全体でのキーワード出現率は過度に意識する必要はありませんが、重要箇所への配置はSEO上効果的です。
内部SEOの基礎を理解する
記事単体の最適化に加えて、サイト全体の内部SEOも成果を大きく左右します。まずXMLサイトマップを整備し、検索エンジンのクローラーが効率的に巡回できる状態にしましょう。またGoogleはモバイルファーストインデックスを採用しているため、スマホ表示に最適化されているかの確認も必須です。
画像にはalt属性を設定し、リンクは関連ページへ適切につなぐとSEO効果が高まります。記事公開前にこうした基礎を固めておくことが、安定した成果につながります。
公開前のチェックリストを作る
記事を公開する直前には、誤字脱字の確認に加え、SEO観点でのチェックを行うことが必須です。以下のポイントを踏まえて、多角的に確認しましょう。
・メタディスクリプションが設定されているか
・画像に代替テキストがあるか
・内部リンクが適切か
・読み込み速度に問題がないか
各要素は、検索結果のクリック率やクローラビリティに直結します。特にメタディスクリプションは検索結果に表示されるため、ユーザーが思わずクリックしたくなるような内容に仕上げることが大切です。
公開後に行うべき施策と戦略方法

記事は公開して終わりではなく、公開後の運用こそが成果を左右します。アクセス解析やSNSでの拡散、リライトによる改善を通じて、記事の価値を継続的に高めていきましょう。最後に、公開後の施策とリライト戦略を紹介します。
記事の宣伝と被リンクを獲得する
公開後すぐにアクセスを集めるには、SNSやメールマガジンなど既存チャネルを活用して告知することが重要です。また、外部メディアでの紹介やプレスリリースを通じて被リンクを獲得できれば、SEO効果を大きく高められます。
被リンクは、検索エンジンにとって信頼性の指標にもなります。記事を第三者が紹介したくなるような「データ」「調査」「テンプレート」などの有益なコンテンツを盛り込むことが効果的です。宣伝と被リンク獲得を組み合わせれば、アクセスの伸びを加速できます。
アクセス解析から改善ポイントを導く
Google AnalyticsやSearch Consoleを使うと、記事の流入数やクリック率、掲載順位などのデータを詳細に把握できます。特にクリック率(CTR)が低い場合は、タイトルやメタディスクリプションの改善に加え、検索順位や表示要素(リッチリザルトなど)も含めて総合的に見直すことが重要。掲載順位が伸び悩んでいる場合は、記事内容の網羅性や内部リンク構造を改善することが効果的です。
数値を根拠に改善を進めれば、感覚ではなくデータに基づいた効率的な運用が可能になります。公開後は必ず定期的にアクセス解析を行い、改善サイクルを回すことが成功の鍵です。
リライトのタイミングを図る
記事の価値を保つには、定期的なリライトが欠かせません。検索順位が落ちてきたタイミングや、情報が古くなったときが見直しの好機。具体的には、新しい情報の追加、重複部分の整理、関連ページへの内部リンク強化などが効果的です。
また、検索ニーズの変化に応じてキーワードを調整することも重要です。公開した記事を放置せず、定期的にメンテナンスすることで、SEO評価の維持・向上につながります。リライトはオウンドメディア運営の必須タスクと位置付けるとよいでしょう。
まとめ
オウンドメディア記事の執筆は、単に文章を書く作業ではなく「戦略的な情報設計」が求められます。本記事で解説した キーワード選定・構成設計・執筆の工夫・SEOチェック・公開後の改善 を順に実践すれば、読者に価値を届けつつ、SEO効果も最大化が可能。記事は一度書いて終わりではなく、更新と改善を重ねることで資産に成長していきます。小さな一記事から積み重ね、自社の強力な集客基盤としてオウンドメディアを育成していきましょう。
「何から始めたらよいかわからない」「記事制作のリソースが足りない」と悩むなら、ぜひCreative Driveにご相談ください。コンテンツ企画から執筆・運用改善までを一気通貫でサポートし、成果につながるオウンドメディア運営をお手伝いします。