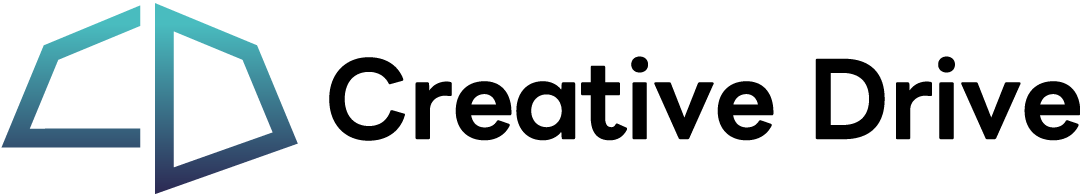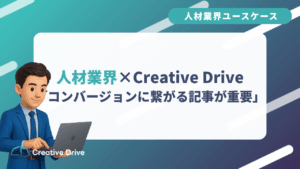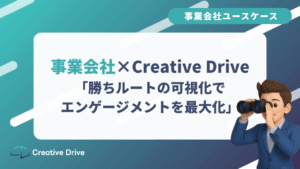広告業界×Creative Drive 「使いやすいだけでなく、アクションも提示」
2025年09月01日
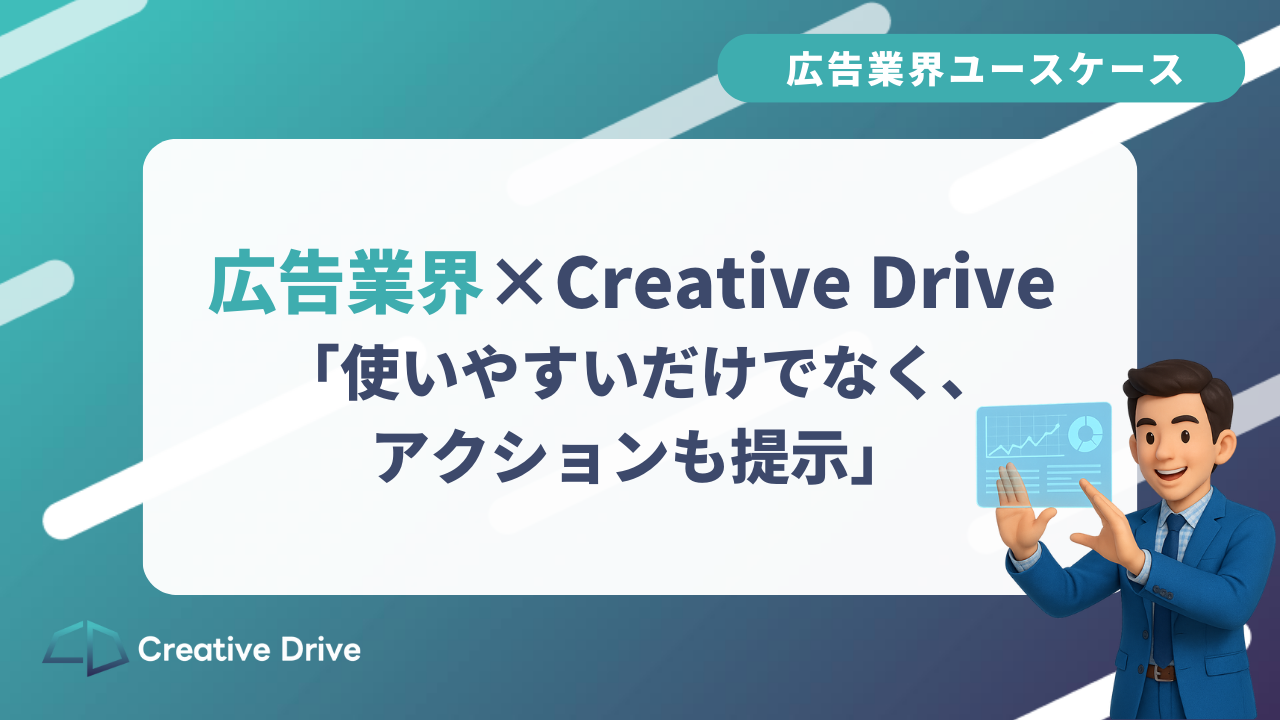
BtoBマーケティングの現場では、DXやAIツールへの注目が高まる一方で、「本当に使えるのか?」「導入によって何が変わるのか?」といった疑問や不安も根強くあります。このユースケースシリーズでは、業界のプロフェッショナルの方にお話を伺い、「Creative Drive」の活用方法について考えます。
今回、お話を伺ったのは、Web系の広告代理店での経験が長い森様。注目している機能、期待する効果などを正直に語っていただきました。
──Creative Driveのサービスサイトや資料をご覧になって、業務や業種で活用できそうだと感じたポイントはありますか。
キーワード軸でアトリビューションを見られる点が良いと感じました。特にBtoB領域では、お客様の課題が顕在化していないことが多く、我々が設定したキーワードだけでは市場を取り切れないケースがあります。直接的なコンバージョンだけでなく、その手前の興味・関心や啓蒙段階に寄与するキーワードを把握する必要があるので、その点がわかるのは有益だと思いました。
──Creative Driveはどのような商材に適しているとお考えですか。
BtoBの場合、商材単価が高いケースが多く、リスティング広告などでは十分な母数を確保できないという悩みを持つ企業に向いていると思います。また、BtoCでも競合に大手が存在し、ビッグワードで戦うのが難しい状況では有効ではないかと考えます。ちょっと角度を変えたワードや、より広い潜在層を狙っていくような戦い方が必要ですね。to Cに関しても活用できると感じました。リスティングで取れるキーワードは、非常にわかりやすいコンバージョン直結型、いわゆる「今すぐキーワード」に当たるものです。
一方で、アトリビューション的に時系列でデータを見られることで、「今すぐキーワード」ではなくても、ノークエリでコンバージョンしているケースが見えてくるのは重要です。リスティングで取れるコンバージョンクエリは競合性が高く、価格も上がりやすい。実際、某大手オンラインクリニック企業と話をした際にも、その点が課題として挙げられていました。
──実際にそういう戦い方をしている会社も多い印象です。
BtoBでビッグワードでは勝てない状況の中、サーチコンソールで年間1件しか検索されないようなニッチワードでも、そのユーザーはコンバージョン率が非常に高い、というケースがありました。そこで、そのキーワードを拾って自動でLPを作成し、上位表示させる仕組みを構築したことがあります。
リスティングでは入札してもクリックや検索がほとんど発生せず不利になるので、その代わりに個別LPを作り、自動化で量産する形を取りました。これによりサイト全体のパワーも蓄積され、BtoBにおけるテールワード戦略として機能しました。潜在ニーズを引き出すというよりも、テールワードを効率的に拾い上げる戦い方に近いと思います。
また、こうしたデータはマーケティングだけでなく、セールスやカスタマーサクセス、さらにはプロダクト開発の優先順位決定にも活用できるはずです。お客様が何に困って問い合わせしたのか、元々どんな興味を持っていたのかといったインサイトが発見できるからです。
営業やCS担当が直接ヒアリングしても、質問の仕方やお客様自身が気づいていない課題のために、本質的なニーズが見えにくい場合があります。熟練の担当者なら引き出せることも、どうしても属人的になりがちです。しかし、行動データから潜在的な動きを読み取ることで、コンバージョンに至るプロセスや途中で離脱するポイントなどを可視化できる。それは非常に価値があると感じています。
──Creative Driveに搭載されている機能の中で、特に業務の効率化や成果向上に貢献しそうなものはどれでしょうか。
成果貢献で言えば、やはり「勝ちキーワードがわかる」という点だと思います。ただ一方で気になったのは、AI技術によって作業時間が半減するとありますが、記事作成時間が90%削減されるのは、AIが自動で文章を書いてくれるからなのか、それとも自動化による効率化の結果なのか、その仕組みを知りたいと思いました。
また、Googleが無料で公開するようなツールは登場した瞬間に業界に大きな影響を与えます。ただ、Googleのツールは上級者向けで初心者には扱いづらい部分がある。その点、御社のように初心者でも使える設計は非常に良いと思います。BtoB SaaSを担当していた際も、クライアントから「利用者はマーケティング初心者だから、専門知識がなくても使えるツールが必要だ」とよく言われました。私たちからすると使いやすいと思うものでも、ユーザー側からは「分析できる」だけでは不十分で、「具体的に何をすればいいか」というアクションが提示されることを求められるのです。
つまり、ある程度知識のある人向けにライターやマーケ担当者が効率的に使えるツールにするのか、それとも完全に初心者でも成果を出せるツールにするのか、そのポジショニングが重要だと感じました。
──こういう有効活用の仕方がある、というアイデアはありますか。
直近で言えば、オウンドメディアの記事作成に役立てられると思います。ただ、それ以外でも企業のマーケティング活動は多岐にわたり、リスティング広告なら「もっと早く成果が出せる」や「この領域は手薄だから入札を強めた方がいい」といった示唆が得られるはずです。また、カスタマージャーニーに沿ったナーチャリングの戦略にも活かせると思います。
BtoBではよくナーチャリングの重要性が語られますが、BtoCでも高額商材や比較検討が長いケースでは同じです。その過程で自社に足りないコンテンツを探し、それをオウンドメディアやホワイトペーパー、記事コラム、メルマガ、セミナーなどで補完していく。その設計に役立てられると感じます。
さらに、商談プロセスの1回目と2回目でどうフォローすべきか、接点を持った顧客にどんなコンテンツや動画を提示するとよいか、といった具体的な施策にも展開できるでしょう。CSにおけるクロスセル・アップセルの設計や、動画や勉強会といった施策の判断材料にもなり得ます。
私自身も、スタートアップ時代にPRを起点にSEO対策を行い、学校法人や自治体を対象にしたプロジェクトで成果を上げた経験があります。予算の少ない中で、PRで話題を作り、それをSEO的に拡散・上位表示につなげ、最終的にはインバウンドでリードの8割を獲得しました。
このように、PRで関心を引き、そこからブログ記事へ誘導し、最終的にリスティングで刈り取る。こうした一連のジャーニーの中でも十分活かせると考えます。
──このPRを起点としたSEO対策というのは、いわゆるリサーチPRの文脈で仕掛けていくイメージでしょうか。
まさにそれです。アンケートを取って一次情報を作り、それをPRの訴求に活かしつつ、アンケートデータをコンテンツに落とし込む。この手法は、to Cでサプリメントを販売していた時に取り組みました。ただ、代理店が介在していたことや、サプリという商材の特性上、CPAや母数の観点では難しい部分もありました。成功事例というよりは取り組みとして実施した、という形です。
一方で、BtoB SaaS領域では参入障壁が低く、競合との差別化が難しいプロダクトが多い。「SEOをやりましょう」と言っても他社と似た記事になってしまう。その中で改めて「自社の強みは何か」を考え直すことが重要だと思います。ユーザーに対して一歩先の提案を提示できなければ、市場そのものを広げられないからです。その点では、マーケットを創り出すような発想が有効だと感じています。
実際、啓蒙サイトを立ち上げ、購入直結ではなく理解促進を経て刈り取る戦略をとったこともあります。当時は代理店から「直コンバージョンを狙うべき」と言われましたが、啓蒙サイトによって市場規模が約10倍に広がりました。さらに、啓蒙サイト×リスティング×リマーケティングの組み合わせで成果を上げた経験もあります。
もう一つの事例として、病院検索サイトにリマーケティングタグを設置し、健康に不安を持つユーザー層へ広告を配信しました。これにより、対象ユーザー数が大幅に増え、Googleの類似オーディエンス機能と組み合わせて効果的にリーチできました。一方で、近い業種の小規模サイトと連携しても母数が少なく効果が薄かったため、「どの段階のユーザーにアプローチするか」が極めて重要だと学びました。
また、がん患者向けのウィッグ販売会社との取り組みでは、直接的なユーザー数が少なく拡大は難しかったのですが、より手前の「病院を探している層」には十分な数があり、そこからナーチャリングしていく戦略が有効であると感じました。
結果として、アフィリエイトに比べても高単価を実現でき、工数も抑えられる月額固定型の施策として成立しました。
──小規模・中規模・大規模組織など組織には大小ありますが、それぞれの業務体制や人材配置は、AIによってどのように変わっていくと思われますか?
小規模組織の場合、自分の手が回らない時に、専門知識があまりない人やインターンなどに任せるといった運用が現実的だと思います。ある程度標準化された仕組みであれば、知識の浅い人でも担当できるのではないかと感じました。
中規模になると、社内の複数部署に対して「こういうことができます」と横断的に働きかける動きがしやすくなります。部門間での調整や共有を通じて、全体最適を意識したマーケティング展開が可能になるでしょう。
大規模になると、人員は豊富ですが一方で組織が複雑になります。その中で「どうやって売上を上げるのか」という文脈でツールや仕組みを導入することがポイントになると思います。
──今後ツールが広がることで、例えば主婦の方でも成果を上げられるようになる、そんな未来が訪れればいいと思っています。
そうですね。ただ現実的には、採用難易度は地方に限らず都内でも高いです。デジタルマーケティング経験者を採用しようとすると年収が高騰し、大手企業に流れてしまう。結果、未経験者を採用して一から育てる必要が出てきますが、それは難しい。だからこそ、初心者や未経験でも成果を出せるツールの意義は大きいと思います。
そうなれば、コンサルタントも無駄な雑務にリソースを割かず、より高次の提案に集中できるはずです。本来なら事業主側で進めてもらいたいことを自動化や効率化で解決し、コンサルタントは付加価値の高い部分に注力できる。そうした形になれば、日本全体の経済成長にもつながると思います。
最終的に重要なのは、ツールの示唆を鵜呑みにするのではなく、それを基に深掘りして「もっとこうした方がいい」と考えることです。私がBtoC企業にいた時も、「答えはお客さんが持っている」という考えを徹底していました。仮説は社内やAIで立てられますが、最終的には顧客に直接確認してブラッシュアップしていく。そのプロセスをいかに早く、丁寧に回すかが大切だと思います。
──確かにいい言葉ですね。「答えはお客さんが持っている」。
本当にそうだと思います。デジタルやウェブの領域ではPDCAを高速で回せますが、BtoBだとリードタイムが長い分、商談を通じて顧客と直接向き合える。毎日何百件も電話して断られる経験も、資産の一つになるはずです。
私自身、営業畑が長かったので感覚的に動くことが多いのですが、このツールは「社内を説得する材料」としても役立つと思いました。データがあることで「なんとなく良さそう」ではなく、事実に基づいて上司や他部署を動かせる。そこが強みだと感じます。
ただ、会社では社外よりも社内調整の方が難しい場合が多い。BtoB SaaSを売っていた時も、クライアントから「このグラフをそのままレポートに使えないのか」と言われたことがありました。それは対外的な施策というより「社内の提案や調整に使うために欲しい」というニーズでした。
代理店であればお金が動くので対応してくれますが、横の部署や上司は「なぜそんな面倒なことをやる必要があるのか」となりがちです。だからこそ、このツールで得られるデータが「社内を動かす材料」としても有効だと思いました。
──Creative Driveを今後、社内や業界内で紹介するとしたら、どのようなポイントを強調すると良いでしょうか。
マーケティングの知識がなくても簡単に使える点です。単に「使いやすい」というよりも、アクションまで提示してくれる点を説明すると良いと思います。
──最後に、ぜひアドバイスをお願いします。
コンセプト自体が面白いと思いますし、今後も機能が追加されていくはずです。「誰もが使える」という点に加え、潜在層からのパイを広げられるようになれば、非常に面白い展開になると感じます。
──ありがとうございました!
Creative Driveは、コンバージョンしたキーワードと経路の効果測定により、ユーザー行動全体の可視化・評価を行うとともに、AIライティングとサイト内分析・改善がセットになったツールです。記事への流入キーワードとそのキーワード別の成果(CV)を可視化し、コンテンツの分析・改善までを一気通貫で支援します。導入企業は6,300社を超え、B2BからEC、メディア運営まで幅広い分野で実績を重ねています。