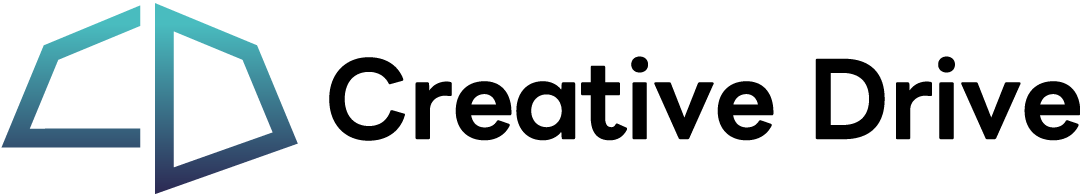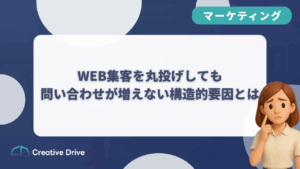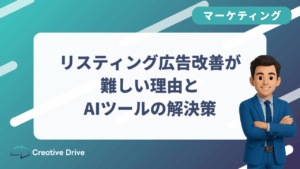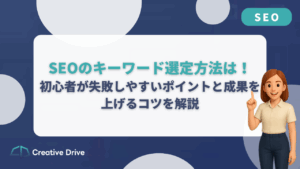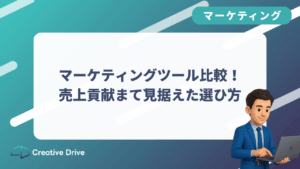BtoBマーケティングで失敗しない!本当に成果が出るリード獲得法とは?
2025年09月16日
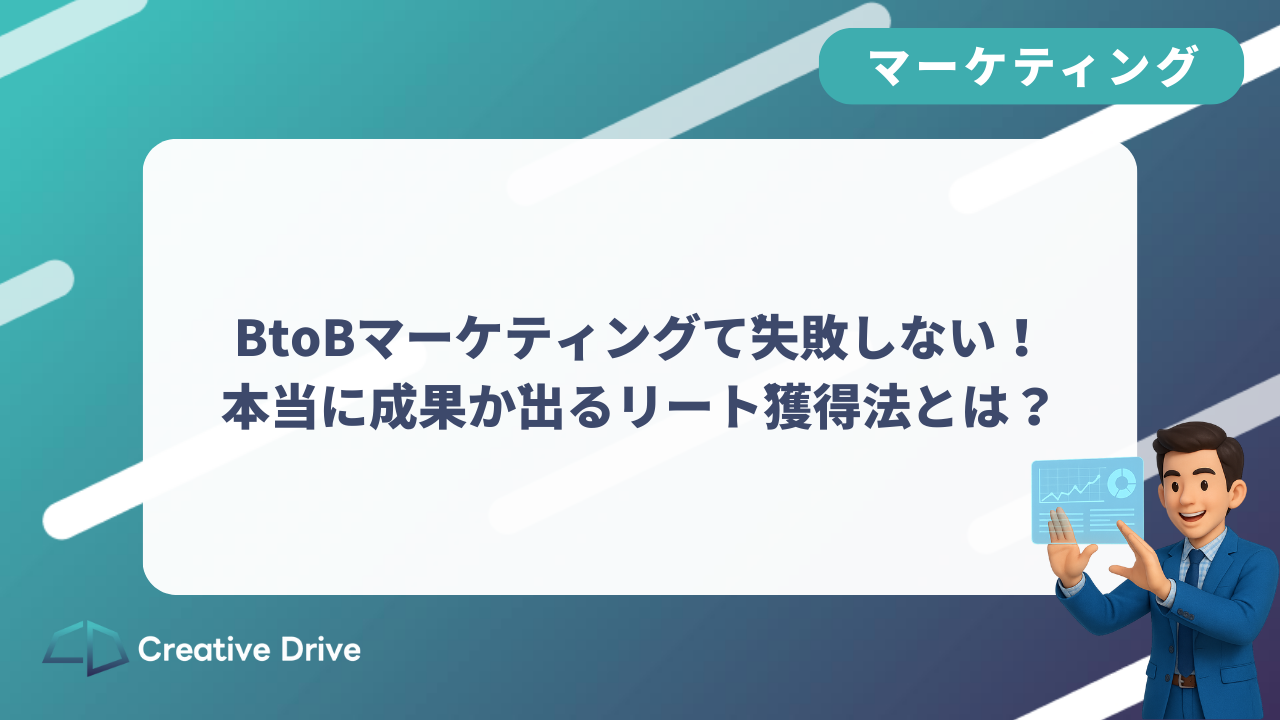
BtoBマーケティングにおけるリード獲得は、単なる集客ではなく、成果に直結する質の高い見込み顧客を安定的に生み出す戦略が求められます。しかし、人的リソースや予算、施策の選定・効果測定の難しさから、思うような成果が出せずに悩む担当者も少なくありません。本記事では、オンライン・オフライン施策の具体例から、最新ツール活用による効率化、長期的な顧客関係構築まで、BtoBリード獲得で失敗しないための実践知をわかりやすく解説します。
目次
BtoBマーケティングにおけるリード獲得の全体像と重要性
BtoBマーケティングにおいてリード獲得は単なる新規顧客リストの収集ではありません。顧客の課題やニーズを深く理解し、最適なタイミングで価値ある情報を提供することが、成果につながるリードの質を左右します。コンテンツによる信頼構築とデータに基づく施策改善が、競争激化するBtoB領域で成果を出し続けるための鍵です。
・リード獲得は顧客リスト収集だけではない
・顧客課題やニーズの深い理解が重要
・信頼構築とデータ活用で成果を最大化
ここでは、リード獲得の全体像とその重要性を3つの視点で解説します。
顧客接点の確保が重要
リード獲得の第一歩は、ターゲット企業や担当者との接点を持つことです。ウェブサイトへの訪問や問い合わせ、展示会やセミナーでの名刺交換など、あらゆるチャネルが顧客接点となります。自社の強みや提供価値を明確に打ち出した情報発信を行うことで、潜在層の興味を引き、初期接点の数を最大化できます。
・ウェブサイト、展示会、セミナーなど多様な接点
・自社の強みや価値を明確に発信
・オンライン・オフライン両方のチャネル活用が効果的
特にオンラインとオフライン双方のチャネルを活用することで、より幅広い見込み顧客にリーチできるのが現代のBtoBマーケティングの特徴です。
情報収集・分析で顧客理解
接点を持った後は、顧客の課題や関心を深く把握することが重要です。Webフォームやアンケート、行動データなどから得られる情報を収集・分析することで、見込み顧客のペインポイントや意思決定プロセスを具体的に理解できます。
・Webフォームやアンケート、行動データの活用
・ペインポイントや意思決定プロセスの把握
・データ活用と仮説検証で施策精度を向上
これにより、単なる名簿リストではなく、確度の高い商談につながるリードへの育成が可能になります。継続的なデータ活用と仮説検証によって、施策の精度を高めていくことが成果につながるポイントです。
長期的な顧客関係構築
BtoB領域では、リード獲得後の長期的な関係構築が欠かせません。商談化や成約までには複数回の接触や情報提供が必要になるため、定期的なメール配信やセミナー招待、役立つコンテンツの提供などを通じて信頼を深めていきます。
・複数回の接触や情報提供が必要
・メール配信やセミナー招待、コンテンツ提供で信頼構築
・顧客の成長や変化に伴走する姿勢が重要
短期的な成果だけを追わず、顧客の成長や変化に伴走し続ける姿勢が、最終的な受注や継続取引につながります。継続的なコミュニケーションを通じ、顧客のファン化を目指すことがBtoBマーケティングにおけるリード獲得の本質です。
オンラインとオフラインを活用したBtoBリード獲得の具体的手法
BtoBマーケティングで安定したリードを獲得するには、オンライン施策とオフライン施策の両輪が不可欠です。
・ウェビナーやSNSは効率的な情報拡散と集客が可能
・展示会やテレアポは直接的な信頼構築や商談化に強み
・ターゲット像や営業プロセスにより双方を補完
・多様なニーズや検討段階の見込み顧客を幅広くカバーできる
今回は代表的な手法ごとに、実践ポイントと成果を最大化する活用方法を解説します。
ウェビナーで専門知識提供
ウェビナーは専門性の高い情報を効率よく多人数に届けられるため、BtoBリード獲得における主要なオンライン施策です。
・導入事例や業界トレンドをテーマに関心を集める
・質の高いリード獲得に直結しやすい
・登録情報やアンケート結果を分析しナーチャリングに活用
・オウンドメディアやSNS連動の集客も効果的
参加者の登録情報やアンケート結果を詳細に分析することで、商談化に向けた個別フォローやナーチャリング施策にも繋げやすいのがメリットです。
展示会で直接対話を促進
展示会は、見込み顧客と直接コミュニケーションを取る絶好の機会です。
・商材やサービスを体験してもらえる
・リアルタイムで疑問や課題に対応できる
・導入検討段階や意思決定層と対面できる
・ターゲット企業リストアップとブースでの印象付けが重要
事前にターゲット企業をリストアップし、ブースでのプレゼンやデモを通じて印象付けることで、アポイントや商談につなげやすくなります。
SNSでブランド認知拡大
SNSは、BtoB領域でもブランド認知やリード獲得の有力チャネルです。
・LinkedInやTwitterがビジネス情報源として活用されている
・専門知見や業界ニュースを発信し接点を増やす
・キャンペーンやイベント情報の拡散が期待できる
・投稿反応やフォロワー属性を分析し施策改善
キャンペーンやイベント情報をSNS経由で発信することで、既存顧客や潜在層からの拡散・紹介も期待できます。
ホワイトペーパーで情報提供
ホワイトペーパーは、見込み顧客が課題解決を模索する段階で有効なリード獲得ツールです。
・業界動向や課題、導入事例を体系的に解説
・自社の専門性や信頼性を訴求できる
・ダウンロード時にリード情報を取得
・ターゲットごとに複数パターン用意で商談化率向上
内容の鮮度や独自性を重視し、ターゲットごとに複数パターンを用意することで、リードの質と商談化率を高められます。
テレアポで直接アプローチ
テレアポは、ターゲット企業にダイレクトな接点を持てるオフライン施策です。
・スピード感ある新規開拓が可能
・決裁者へ直接アプローチできる
・事前リサーチとターゲティングが重要
・ヒアリング内容を後続施策に活用し成果最大化
アポイント獲得だけでなく、ヒアリングを通じて顧客の課題感や意思決定プロセスを把握し、後続のオンライン施策や資料送付、ナーチャリングに活用することで、成果を最大化できます。
成果に直結するBtoBリード獲得施策の選定基準と実践ポイント
BtoBマーケティングでリード獲得の成果を最大化するには、施策ごとの選定基準や実践時のポイントを明確に押さえる必要があります。なぜなら、施策の選び方ひとつで費用対効果やリードの質が大きく変わるからです。
・施策ごとの選定基準と実践ポイントが重要
・ターゲット具体化から効果測定まで解説
・自社に合った戦略構築のヒントを紹介
ここでは、ターゲットの具体化から効果測定、リードの選別、さらには顧客ニーズや予算への最適化まで、成果に直結する施策の選び方と運用のポイントを解説します。自社に合った戦略構築のヒントとしてご活用ください。
ターゲット設定の精緻化
自社サービスの価値を最大限に届けるためには、ターゲット設定の精緻化が欠かせません。まずは理想的な顧客像(ペルソナ)を明確にし、その属性や業種・役職・課題まで細かく定義します。
・理想顧客像(ペルソナ)を明確化
・属性・業種・役職・課題を細かく定義
・関与者ごとの行動や意思決定プロセスを把握
BtoB領域では意思決定者や現場担当者など複数の関与者がいるため、各層の情報収集行動や意思決定プロセスの違いを把握しましょう。これにより、訴求ポイントやコンテンツの切り口が具体化され、リードの質とCVR向上に直結します。実際、ターゲティング精度を高めた企業は無駄なアプローチが減り、商談化率も向上する傾向があります。
施策の効果測定で改善
どの施策が成果に貢献しているかを可視化し、改善を続けることがBtoBリード獲得の成功には不可欠です。たとえば、アクセス解析やCRM連携による数値把握に加え、リード獲得後の商談化・成約率の追跡が重要となります。
・施策ごとにKPIを設定・定期測定
・アクセス解析やCRM連携で数値把握
・効果が薄い施策の見直しが可能
施策ごとにKPIを設定し、定期的に効果測定を行うことで、効果が薄い施策の見直しや重点配分の最適化が可能です。また、データに基づくPDCAサイクルを回すことで、施策の再現性と持続的な改善体制を構築できます。効果測定の徹底が成功企業の共通項です。
質の高いリードを選別
大量のリードを獲得しても、成約につながらなければ意味がありません。BtoBマーケティングでは、獲得したリードをスコアリングや属性分析で選別し、優先順位をつけることが大切です。
・リードをスコアリングや属性分析で選別
・問い合わせ内容や接触履歴で有望度評価
・営業との連携で選別基準を継続的に改善
たとえば、問い合わせ内容や過去の接触履歴、企業規模や役職などをもとに有望度を評価します。また、営業との連携により、現場で実際に成約に至ったリードの特徴をフィードバックし、リード選別基準を継続的にブラッシュアップしましょう。これにより、営業効率と成約率の両方を高められます。
顧客のニーズに応える施策
リード獲得施策で最も重視すべきは、顧客のリアルなニーズに応えることです。BtoB市場では課題解決型の情報提供や、自社独自のバリュープロポジションを明確に伝えるコンテンツ設計が成果に直結します。
・課題解決型の情報提供が重要
・実務に役立つ具体的なコンテンツ設計
・検討フェーズに合わせたアプローチ最適化
たとえば、「業界別の成功事例」や「課題別のソリューション解説」など、実務に役立つ具体的な情報が求められます。さらに、顧客の検討フェーズに応じてコンテンツやアプローチ方法を最適化することで、リードの質とエンゲージメントが向上します。顧客理解を深めるほど、競合との差別化も図りやすくなります。
予算に合わせた施策選定
限られた予算で最大限のリード獲得効果を出すには、施策ごとのコストとリターンを具体的に比較し、優先順位を見極めることが肝心です。
・コストとリターンを比較して施策を選定
・内製と短期成果の手法を組み合わせる
・コスト構造と運用体制の最適化が重要
自社で内製できる施策や、短期間で成果が見込める手法を組み合わせることで、リスクを抑えつつ成果を最大化できます。特に、運用の属人化や外注費の高騰に悩む企業は、コスト構造の見直しやツール活用による効率化を検討しましょう。継続的なリード獲得には、予算配分の最適化と同時に運用体制の柔軟性も求められます。
Creative Driveのような月額制AIライティングツールを活用することで、外注費用の大幅削減と高品質なリード獲得施策の内製化が可能です。無料デモ予約も受付中なので、費用対効果に悩む場合は一度導入相談をおすすめします。
効果的なリード獲得のためのターゲット設定とカスタマージャーニー設計
BtoBマーケティングにおいて、リード獲得の成果を最大化するには、ターゲットの明確化とカスタマージャーニーの綿密な設計が欠かせません。
・自社の強みや提供価値だけでなく顧客行動を可視化
・一連の行動心理や接点を把握
・施策選定の精度向上が可能
この記事では、実践的なターゲット設定手法と、リード獲得に直結するカスタマージャーニー設計のポイントについて具体的に解説します。
ペルソナを明確に設定
リード獲得施策の第一歩は、ペルソナの明確化から始まります。単なる属性や業種だけでなく、役職や意思決定権、抱える課題、情報収集の行動パターンまで深く掘り下げることが重要です。
・役職や意思決定権、課題を具体的に
・「部長クラス」「予算100万円以上」など詳細設定
・複数ペルソナを用意しデータで定期更新
複数のペルソナを用意し、現実の商談データやヒアリング結果を定期的に反映させてアップデートする運用体制も成果向上につながります。
カスタマージャーニーを描く
ペルソナが定まったら、次はカスタマージャーニーを設計します。見込み顧客が「どのタイミングで」「どのチャネルを通じて」情報に触れ、どのように興味・関心を高めていくのか、その道筋を具体的に可視化することが肝要です。
・各フェーズで最適なコンテンツを配置
・行動心理や検討障壁も洗い出す
・離脱率抑制とCV率向上につなげる
情報収集段階ではホワイトペーパーやウェビナー、比較検討フェーズでは事例記事やデモ体験など、各ステージごとに最適なコンテンツ配置とアクション動線を意識しましょう。顧客の行動心理や検討障壁も洗い出し、解決策を予め用意することで、離脱率の抑制とCV率向上が期待できます。
顧客の課題を深掘り
ターゲット設定とジャーニー設計を通じて、最も重要なのは「顧客が本当に困っていること」を深く理解することです。ヒアリングやアンケート、過去問い合わせ内容の分析を通じて、表面的な要望だけでなく根本的な課題や未顕在ニーズの把握に努めましょう。
・現場担当者と経営層の視点を整理
・工数負担やCV未増加など具体的課題を特定
・根本的なニーズを把握し差別化ポイントを明確化
たとえば「記事制作の工数が負担」「SEO順位は取れているがCVが増えない」など、現場担当者と経営層それぞれの視点を整理することが、説得力あるコンテンツや提案設計の土台となります。課題を的確に捉えることで、他社との差別化ポイントもより明確になります。
行動データを活用
リード獲得の現場では、顧客の行動データを戦略的に活用することが求められます。Webサイトの閲覧履歴や資料DL、問い合わせ前後の動線分析など、多様なデータを組み合わせることで、各ペルソナがどのステージでどんな情報を求めているかを把握できます。
・GA4やヒートマップ、MAツールを活用
・仮説と実際の行動を照らし合わせPDCAを回す
・データ可視化と現場フィードバックを両立
GA4やヒートマップ、MAツールなどを活用し、仮説と実際の行動を照らし合わせてPDCAを回すことで、施策の精度が飛躍的に向上します。データの可視化と現場フィードバックを両立させる運用体制が、成果の持続的な最大化につながります。
継続的な改善を実施
ターゲット設定やカスタマージャーニー設計は、一度作って終わりではありません。市場環境や競合の動き、顧客ニーズの変化にあわせて、定期的な見直しと改善を行うことが重要です。
・KPIやCVデータで成果と仮説のギャップを検証
・必要に応じてペルソナやジャーニーをアップデート
・継続的な改善サイクルで成果を中長期的に支える
KPIやCVデータをもとに、実際の成果と施策仮説のギャップを検証し、必要に応じてペルソナやジャーニー、コンテンツそのものをアップデートしましょう。こうした継続的な改善サイクルが、BtoBリード獲得の成果を中長期的に支えます。
リード獲得後のナーチャリングと営業連携で成果を最大化する方法
BtoBマーケティングにおいてリードを獲得した後は、単にリスト化するだけでなく、効果的なナーチャリングと営業連携によるアプローチが必須です。見込み顧客を段階的に育て、適切なタイミングで営業にパスすることで、成約率やLTVの最大化につながります。
・リードの育成と適切な営業へのパスが成約率向上に直結
・ナーチャリング体制や情報共有の徹底が不可欠
・リード状態に応じた施策設計が成果を生み出す
ナーチャリング体制の構築や情報共有の徹底、リードの状態に応じた施策設計など、成果を生み出す運用ポイントを具体的に解説します。
インサイドセールスで育成
インサイドセールスは、獲得したリードに対して非対面チャネルで継続的にアプローチを行う役割です。
・メール配信やオンライン面談、ウェビナーを活用
・顧客の興味や課題感を把握し購買意欲を高める
・営業部門との役割分担で効率的なリード育成を実現
BtoB領域では検討期間が長くなりがちですが、インサイドセールスの細やかなフォローによりリードの離脱を防ぎ、確度の高い案件の創出に貢献します。営業部門との役割分担を明確にすることで、効率的なリード育成が可能です。
CRMで情報を共有
CRM(顧客管理システム)は、リード情報ややりとり履歴を一元管理する基盤となります。
・過去接点や興味コンテンツ、商談進捗をリアルタイム共有
・情報の属人化を防ぎチーム全体で顧客理解を深める
・パーソナライズされたコミュニケーションを実現
例えば過去の接点、興味を示したコンテンツ、商談化の進捗などをリアルタイムで共有することで、各担当者が最適なアクションを選択できます。情報の属人化を防ぎ、チーム全体で顧客理解を深めながら、リードごとにパーソナライズされたコミュニケーションを実現できる点が大きなメリットです。
リードの熱度に応じた対応
リードごとに興味関心や検討度合いは異なります。スコアリングや行動データで「今すぐ客」と「これから客」を見極め、最適なアプローチを実施します。
・資料DLやセミナー参加などアクションで対応レベルを調整
・熱度の高いリードは営業が即アプローチ
・検討段階のリードにはナーチャリングコンテンツを提供
例えば資料ダウンロードやセミナー参加など、アクションの回数や質によって対応レベルを調整します。熱度の高いリードには営業が即アプローチし、まだ検討段階のリードにはナーチャリングコンテンツを提供するなど、段階的な対応が成約率アップに直結します。
定期的なフォローアップ
リード育成には、一定間隔でのフォローアップが不可欠です。
・メールマガジンやニュースレターで関係性を維持
・リード状況変化に合わせ適切な情報を提供
・検討再開タイミングで優先的に選ばれる状態を目指す
BtoBでは意思決定プロセスが長期化するため、接点を絶やさず「検討が再開されたタイミング」で優先的に選ばれる存在になることが重要です。営業現場との連携により、フォロー内容や頻度も最適化しましょう。
営業とマーケティングの連携強化
営業とマーケティングの連携が成果最大化のカギを握ります。
・リード育成方針やアプローチ基準の共通認識化
・定例ミーティングやSLA設計で役割と指標を明確化
・部門間の摩擦減少と全体最適で成果創出
両部門でリード育成方針やアプローチ基準を共通認識として持つことで、リードの質向上と機会ロス防止が実現します。例えば定例ミーティングやSLA(サービスレベルアグリーメント)の設計により、どの段階でリードを営業に引き渡すか、どの指標を重視するかを明確化しましょう。これにより、部門間の摩擦を減らし、全体最適での成果創出が可能となります。
BtoBリード獲得における施策の効果測定と改善サイクルの構築
BtoBマーケティングにおいて、リード獲得施策は「やりっぱなし」では成果が頭打ちになります。施策ごとの効果測定と、根拠に基づく改善サイクルの構築が不可欠です。
・各施策のKPIやROIを可視化
・定期的なデータ分析で優先順位最適化
・オウンドメディア運営責任者にとって重要な業務
・成果を再現性高く伸ばすプロセスが必要
ここでは、成果を再現性高く伸ばすための具体的なプロセスを解説します。
KPI設定で成果を可視化
リード獲得の成果を最大化するには、まず施策ごとに適切なKPI(重要業績評価指標)を設定する必要があります。
・「記事からの問い合わせ件数」「資料ダウンロード数」など目的別に指標を定める
・KPIは数値で施策の成否を判断でき、社内共有や意思決定の根拠となる
・短期・中長期で追う指標を分けることで目標管理を最適化
・シンプルな指標からスタートし、状況に応じて柔軟に見直す
KPIは施策の成否を数値で判断できるため、社内共有や意思決定の根拠にもなります。また、短期・中長期で追うべき指標を分けることで、現場担当者と経営層双方が納得できる目標管理が可能です。KPIは変数が多いほど複雑になるため、最初はシンプルな指標からスタートし、状況に応じて柔軟に見直すことがポイントです。
効果測定ツールを活用
施策の効果測定において、ツールの活用は欠かせません。
・GoogleアナリティクスやMAツールで流入経路・CV数などを可視化
・チャネル別の貢献度を把握し、投資や優先順位判断に活用
・データ分析・レポーティング体制の構築が重要
・ツール導入時は活用目的とデータ粒度を事前に定義
さらに、施策ごとに「どのチャネルが最もリード獲得に貢献しているか」を把握することで、次回の投資判断や優先順位付けに役立ちます。現場では、データ取得後の分析・レポーティング体制も重要です。ツール導入時は、活用目的と取得データの粒度を事前に定義し、無駄な計測や集計作業を省きましょう。
定期的なデータ分析
単発の効果測定で満足せず、定期的にデータをモニタリング・分析する姿勢が成果拡大には不可欠です。
・週次・月次でKPI進捗やボトルネックをチェック
・表面的な数値変動だけでなく要因分析・仮説立てが重要
・ホワイトペーパー経由リード減少時は多角的に分析・改善
・分析の属人化を防ぎ、フォーマットや指標を統一してノウハウ蓄積
分析は属人化しやすいため、フォーマットや指標を統一し、チーム全体でノウハウを蓄積することが大切です。
施策の優先順位を調整
複数の施策を同時展開するBtoBマーケティングでは、リソース配分と優先順位の見直しが常に求められます。
・効果測定やデータ分析でROIの高い施策にリソースを集中
・成果が頭打ちの施策は一時縮小や再設計も検討
・短期成果と中長期ブランディングのバランスが重要
・過去データや競合動向を参考に合意形成を図る
こうした柔軟な施策運営が、継続的なリード獲得の成長を支えます。
継続的なPDCAサイクル
BtoBリード獲得で成果を出すためには、一過性の改善で終わらせず、施策ごとにPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを継続的に回し続けることが不可欠です。
・計画・実行・効果測定・改善アクションを繰り返す
・市場や顧客の変化に柔軟に対応できる体制を築く
・具体的なアクションプランに落とし込み、チームで進捗共有
・定期的なレビュー会議やチェックリストの活用も有効
定期的なレビュー会議やチェックリストの活用も有効です。
Creative Drive導入で実現するBtoBマーケティングのリード獲得効率化
BtoBマーケティングの現場では、リード獲得の効率化が常に大きな課題となります。競合が激化する中、自社オウンドメディアの集客力やリードの質を向上させるには、最新のテクノロジーと運用ノウハウの両立が不可欠です。Creative Driveは、AIライティングによる記事制作の効率化や、コンバージョン最適化、行動分析、内製化支援などをワンストップで提供し、リード獲得プロセス全体の最適化を実現します。ここでは、各機能がどのようにBtoBマーケティングの課題解決に寄与するかを具体的に解説します。
・リード獲得の効率化がBtoBマーケティングの重要課題
・最新テクノロジー×運用ノウハウが必要不可欠
・Creative Driveは記事制作〜分析〜内製化まで一気通貫
・リード獲得プロセス全体を最適化できる
AIライティングで効率化
Creative DriveのAIライティング機能は、従来の手動記事作成に比べて圧倒的な効率化を実現します。例えば、1記事あたり数時間かかっていた執筆作業が、大幅に短縮されるだけでなく、記事の品質も安定します。AIは顧客の検索意図と自社のバリュープロポジションを紐づけ、単なるSEO対策ではなく、実際のコンバージョンへ直結するコンテンツを自動生成。これにより、オウンドメディア運営者は企画や戦略立案など、より付加価値の高い業務にリソースを集中できます。
・AIで記事制作を大幅効率化
・品質の安定と短時間執筆を両立
・顧客ニーズと自社価値を反映
・運営者は企画や戦略に集中できる
コンバージョン最適化
リード獲得においては、単なる流入数だけでなく、実際に問い合わせや商談につながるコンバージョン率の最大化が重要です。Creative Driveは独自のアルゴリズムにより、各記事のCTA配置や導線設計を最適化。ユーザーの行動データを基に、コンバージョンの障壁となるポイントを自動判別し、記事の修正提案も行います。そのため、流入数が増えてもCVにつながらない、というよくある悩みを根本から解消できます。
・CV率最大化が重要なポイント
・独自アルゴリズムでCTAや導線を最適化
・ユーザー行動を基に障壁を自動判別
・流入増でもCVしない悩みを解消
トラッキングで行動分析
このサービスのトラッキング機能は、Google AnalyticsやSearch Consoleでは取得できない「検索キーワードとCVユーザーの行動」を可視化します。オウンドメディアの運営者は、どの記事がどのキーワードから流入し、どのような経路でコンバージョンに至ったかを一目で把握可能です。これにより、仮説の精度や施策の再現性が向上し、無駄な施策を減らして確実に成果につなげる運用改善が実現します。
・検索キーワードとCV行動を可視化
・記事ごとの流入・CV経路が一目で分かる
・施策の再現性向上と無駄な運用削減
・確実に成果へとつなげる改善が可能
内製化支援プログラム
Creative Driveは、単なるツール提供にとどまらず、完全内製化を目指す段階的な支援プログラムも用意しています。導入初期はツールの使い方やPDCAの回し方を丁寧にサポートし、半年以降はeラーニングやワークショップを通じて自社運用のノウハウを徹底的に共有。これにより、外注コストを抑えながら、継続的な成果改善と運用体制の強化が可能となります。
・段階的な内製化支援プログラムを提供
・初期はツール活用・PDCAをサポート
・半年以降はeラーニング・ワークショップ実施
・外注コスト削減と運用体制強化が可能
記事ごとのCV貢献度分析
オウンドメディアの成果を最大化するには、記事ごとのコンバージョン貢献度を可視化し、高貢献記事へのリソース集中と改善サイクルを回すことが不可欠です。Creative Driveでは、独自のトラッキングタグを利用して、各記事のCV経路やユーザー行動を詳細に分析。これにより、単なるPVや検索順位ではなく、実際の売上や問い合わせに寄与した記事を特定し、戦略的な記事リライトや新規コンテンツ制作に活かせます。
・記事ごとのCV貢献度を可視化
・高貢献記事へのリソース集中が可能
・トラッキングタグで詳細な行動分析
・売上や問い合わせに寄与した記事を特定できる
BtoBリード獲得で成果を出すための行動ステップ
BtoBマーケティングにおいてリード獲得の成果を最大化するには、戦略的な行動ステップの設計が不可欠です。
・目的設定から施策選定、部門間連携、継続的な改善まで各プロセスが重要
・単発の施策ではなく、全体設計が成果に直結
・現場で実践しやすい具体策を行動ステップごとに解説
ここでは、実際に成果に直結しやすい行動ステップごとにポイントを整理し、現場での実践に役立つ具体策を解説します。
リード獲得の目的を設定
リード獲得活動を始める際、まず最初に明確な目的を設定することが重要です。
・「月間〇件の有効リード獲得」など数値目標を具体化
・ターゲット層や認知拡大など明確な指標を設定
・「なぜリードが必要か」「どの指標を重視するか」をメンバーで共有
目的が曖昧なままでは、施策が散漫になりやすく、得られたリードの質や量にもムラが生じてしまいます。はじめに「なぜリードが必要なのか」「どの指標を重視するのか」をメンバー間で共有し、認識を統一しましょう。
効果的な施策を選定
リード獲得施策は、自社の目的やターゲット属性に合致したメニュー選定が成果の分かれ目です。
・検討初期層にはホワイトペーパーやウェビナーが有効
・中長期育成にはメールマガジンやセミナーを活用
・過去データや競合状況を参考にROIの高いチャネルへ集中
施策ごとに明確なKPIを設定し、効果検証の仕組みを組み込むことで、次のアクションにつなげやすくなります。
営業とマーケが連携
BtoBリード獲得でよくある失敗は、マーケティング部門と営業部門の連携不足です。
・リード定義や評価基準を両部門で合意
・リード情報の共有・フィードバックを定期的に実施
・インサイドセールスやSFA/CRMツールの活用も有効
まずは社内でのコミュニケーション設計が肝となります。
継続的な改善を実施
リード獲得活動は一度設計すれば終わりではありません。
・定期的な施策分析とPDCAサイクルの実践
・毎月のKPIレビュー・施策ごとの成果分析が重要
・データに基づく客観的な判断を重視し、運用フローを定着化
最終的には、社内に定着した運用フローとして継続できる体制づくりを目指しましょう。
まとめ
BtoBマーケティングにおけるリード獲得は、単なる集客数の拡大ではなく「質の高い見込み顧客をいかに継続的に創出し、成果につなげるか」が本質です。オンライン・オフライン双方のチャネルを戦略的に活用し、ターゲット設定やカスタマージャーニー設計、効果測定とPDCAサイクルを徹底することで、初めて安定した成果と競合優位性を築くことができます。しかし、多くのメディア運営責任者が直面するのは「人的リソースや予算の制約」「コンテンツ品質のばらつき」「SEOとCV最大化の両立」といった運用上の壁です。このような課題に対し、Creative DriveはAIパーソナライズコンテンツと独自トラッキングによるCV経路分析を強みに、戦略設計から記事制作・効果測定・改善まで一気通貫で支援。SEO集客だけでなく、実際の問い合わせ・受注に直結する“成果重視”のリード獲得体制を構築できます。月額制でコスト効率よく、内製化もサポートしているため、外注費用や運用負荷に悩む方にも最適です。まずはCreative Driveの機能を自社で体験し、個別課題に合わせたご提案を受けてみてください。現在、無料デモを受付中です。ぜひ 無料デモ予約ページ よりご相談ください。