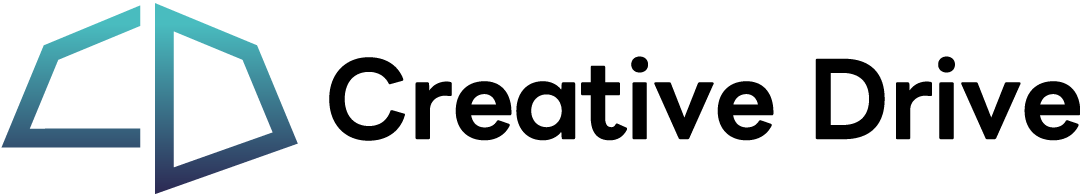初心者でもサイト分析のやり方わかる!目的・手法・ツール・改善ポイントまで解説
2025年08月12日

Webサイトは作って終わりではなく、改善と最適化を重ねて初めて成果が見込めます。そこで必要になるのが「サイト分析」です。ユーザー行動を可視化し、課題発見や改善施策の立案に役立つサイト分析は、マーケティングの中心的な役割を担っています。
今回は、サイト分析の基本から具体的なやり方、活用ツール、よくある失敗まで、実践的な観点で網羅的に解説します。
目次
サイト分析とは?

サイト分析とは、Webサイト上でのユーザーの動きや行動データを収集・解析し、課題の特定や改善施策の検討に活かすプロセスを指します。訪問者数だけでなく、離脱ページや滞在時間、クリック箇所なども可視化できます。数字の裏側にあるユーザー心理を読み取ることで、より的確な改善が可能。単なる数字の収集ではなく、“サイトの現状把握と未来の設計”に欠かせない業務なのです。
アクセス解析との違いは?
アクセス解析はサイトに訪れたユーザーの数やセッションの推移など、比較的シンプルな数値の記録・分析を中心としています。一方、サイト分析では定量データに加えて、ユーザー行動や意図、感情といった定性的な情報も含めて分析対象にします。つまり、アクセス解析はサイト分析の一部であり、後者はより総合的・戦略的な取り組みといえるでしょう。
どんな課題発見に活かされる?
サイト分析は、CVR(コンバージョン率)の改善や離脱ポイントの特定、UI/UXの最適化など、幅広い課題の発見に役立ちます。たとえば、ランディングページの直帰率が高ければ「導線が悪い」「情報が不足している」といった仮説が立てられます。このような気づきをもとに、デザインやコンテンツの改善へとつなげることが可能。課題発見から施策立案まで、一貫した流れで活用できるのが特徴です。
サイト分析の目的・成果につながる考え方

サイトにおいての成果は、分析ツールを使うだけでは得られません。大切なのは「なぜ分析するのか」「どこに向かうべきか」を明確にすることです。ここでは、目的意識を持ったサイト分析の視点を3つに分けて解説します。
分析の目的を明確にする重要性
サイト分析は「数字を見る」ものではなく、目的を持って行うことで初めて意味を持ちます。目的が曖昧なままだと、得られたデータも活用できず、結果的に改善にはつながりません。たとえば「問い合わせ数を増やしたい」という目的がある場合、離脱ポイントやCTAクリック率に注目するのがおすすめです。また目的が明確であれば、必要なデータや指標も自然と見えてくるようになります。
KGI・KPIを意識した視点
KGI(最終目標)やKPI(中間目標)を設定することで、サイト分析はより戦略的になります。たとえば「売上を2倍にしたい」というKGIがある場合、目標を達成するには「月間訪問者数の向上」や「CV率の改善」といったKPIが必要です。目標に対して適切な指標を追うことで、数値変化の因果関係が明確になります。分析がブレなくなるため、結果として改善の精度も高まります。
分析のその先にある改善アクション
分析で得た数値や気づきを“見るだけ”で終わらせてしまうと、何も成果にはつながりません。重要なのは、そこから改善施策を立てて、実行・検証するアクションの流れを持つことです。たとえば「滞在時間が短い」という結果が出た場合、原因は情報不足かUIの問題かを仮説として立てる必要があります。また、仮説をもとに改善施策を立案・実行していくことも成果への近道になります。
サイト分析の主な手法

サイト分析にはさまざまなアプローチがあり、大きく「定量分析」「定性分析」「テスト手法」の3つに分類できます。次に、それぞれの手法の特徴と活用場面を具体的にご紹介します。
定量分析
定量分析とは、数値データを中心にユーザーの行動や傾向を読み取る方法です。代表的なツールにGoogleアナリティクス(GA4)があり、ページビューや直帰率、セッション時間、コンバージョン率などを測定できます。数値で傾向を掴めるため、課題の発見や変化の比較がしやすいのが特徴です。仮説立案や改善の出発点として有効であり、すべてのサイト運営者が取り入れたい基本手法です。
定性分析
定性分析では、ユーザーの行動や心理を“感覚的に”捉えることが可能です。たとえばヒートマップを使うと、「どこをクリックしたか」「どこで離脱したか」「どの範囲までスクロールされたか」などを視覚的に把握できます。また、ユーザーテストを行うことで、実際の利用シーンにおけるつまずきや疑問点も見えてきます。数字では読み取れない“なぜ”を探るうえで非常に役立つ手法です。
A/Bテストやユーザーテストの活用
改善施策の効果を検証するには、仮説をもとにしたテスト運用も必要です。A/Bテストは、異なるパターンのページをユーザーに同時表示し、どちらがより良い成果を出すかを比較する手法です。デザインや文言の微細な違いが成果にどう影響するかを科学的に測定できます。一方、ユーザーテストはリアルな使用感を観察するため、初期段階の改善アイデア収集にも効果的です。
具体的なサイト分析のやり方【ステップ別】

サイト分析を効果的に行うには、正しい順序を踏むことが大切です。感覚だけで進めるのではなく、目的の設定から改善施策の実行まで、一貫したステップで進めることが成功のカギとなります。ステップを順にみていきましょう。
ステップ1:目的とゴールを明確にする
分析を始める前に、まず「何を知りたいのか」「何を改善したいのか」という目的を定める必要があります。漠然とデータを眺めても、意味のある示唆は得られません。たとえば「ECサイトの購入率を上げたい」という目標の場合、購入までの離脱ポイントを把握することが必要です。目標が明確になっていれば、後の指標選定やツール活用にも無駄がなくなり、分析の質が大きく向上します。
ステップ2:使用する指標を決定する
目的が定まったら、それに応じて追うべき指標(KPI)を選定します。ページビューや直帰率、コンバージョン率、滞在時間など、多数の指標の中から本質的なものを絞り込むことが大切です。たとえば資料請求を増やしたい場合は、資料ページの遷移率やCTAボタンのクリック数が重視されます。関係のない数値ばかりを追うと分析の軸がブレてしまうため、目的との一貫性を意識しましょう。
ステップ3:ツールでデータを収集する
分析に必要なデータを集めるには、信頼できるツールの活用が欠かせません。Googleアナリティクスやサーチコンソール、ヒートマップツールなどを目的に応じて組み合わせて使いましょう。複数ツールを横断的に活用することで、数値と行動の両面からサイトの状態を把握できます。ツールの設定ミスやトラッキング漏れには注意が必要ですが、正しく運用すれば非常に有益な情報が得られます。
ステップ4:結果をもとに課題を抽出する
収集したデータをただ眺めるだけでは意味がありません。重要なのは、数値の背景にあるユーザー行動やサイト構造上の問題を読み取ることです。たとえば、特定のページで直帰率が高ければ、「内容が期待と異なる」「導線が分かりにくい」といった課題が想定されます。異常値や傾向をもとに仮説を立てることで、改善の方向性が具体化されていきます。数値はあくまで“気づきのヒント”なのです。
ステップ5:改善仮説を立て、施策に落とし込む
課題が見えたら、それに対する改善仮説を立て、具体的な施策へと落とし込んでいきます。たとえば、お問い合わせフォームでの離脱率が高い場合、入力項目が多すぎる可能性が考えられます。仮定を立てると、入力欄を減らして、UIを改善するなどの明確なアクションへと展開するでしょう。施策は一度で完璧にする必要はなく、検証を繰り返しながら精度を高めていくことが重要です。
サイト分析に役立つ主要ツール

サイト分析を正確かつ効率的に行うためには、適切なツールの活用が欠かせません。続いては、定量・定性の両面で役立つ代表的な分析ツールを4つ紹介し、それぞれの強みや活用ポイントを解説します。
Googleアナリティクス(GA4)
Googleアナリティクスは、Webサイトの訪問者数や行動パターンを把握するための代表的な定量分析ツールです。最新のGA4では、従来のセッションベースからイベントベースへとモデルが進化し、ユーザーの行動をより細かくトラッキングすることが可能。ページごとの直帰率やスクロール深度などを確認しやすく、改善すべきポイントの洗い出しにも役立ちます。無料で使える点も導入のしやすさにつながっています。
Googleサーチコンソール
Googleサーチコンソールは、検索エンジン上での自社サイトのパフォーマンスを分析できるツールです。特定キーワードでの表示回数・クリック数・掲載順位などを可視化できるため、SEOの強化にも活用されています。インデックス登録の状況やモバイル対応の問題点も確認でき、検索流入に関する技術的な課題発見にも有効です。GA4と併用することで、流入から行動まで一貫した分析が可能になります。
ヒートマップツール
ヒートマップは、ユーザーが実際にどの部分を見て、どこでクリックしたのかを視覚的に表示する定性分析ツールです。MouseflowやContentsquareなどを使えば、スクロール位置・ホバー率・離脱箇所などの情報を色で直感的に把握できます。UI/UXの改善やコンテンツの最適化に非常に役立つため、定量データと併せて活用することで、より立体的なサイト分析が実現します。
その他に便利な可視化・レポート作成ツール
分析データをチームで共有したり、視覚的にわかりやすくレポートにまとめたりするには、可視化ツールの活用も有効です。たとえば、Googleデータポータル(Looker Studio)を使えば、GA4やサーチコンソールのデータを連携し、ダッシュボード形式で可視化できます。レポートの自動更新も可能なため、定期的なモニタリングや経営報告にも役立つでしょう。分析の“見える化”は社内共有にも大きな効果をもたらします。
サイト分析でよくある3つの失敗例

サイト分析は効果的な運用につながる一方で、進め方を誤ると成果が出にくくなります。ここからは、よく見られる失敗を解説し、対策法を具体的に紹介します。
数字を眺めるだけで終わってしまう
分析ツールを導入しても、得られた数値を眺めるだけで終わってしまうケースは少なくありません。「PVが減っている」「直帰率が高い」などの現象を確認するだけで、そこから何もアクションにつながらないことが原因です。こうした事態を避けるには、数値を見たうえで“なぜそうなったのか”を考える癖をつけることが大切です。分析の目的や仮説を常に意識し、改善の第一歩へとつなげましょう。
仮説が立たず改善施策につながらない
データを見ても、具体的な仮説や施策に落とし込めないという壁に直面することがあります。この現象はそもそもの目的設定が曖昧だったり、見るべき指標を絞れていなかったりする場合に多く見られるでしょう。仮説を立てないと、次のアクションが決まらず、分析が堂々巡りになってしまいます。小さな気づきでも、「こうではないか?」という視点から検討を始めてみることが有効です。
部分最適にとどまり全体がよくならない
ページ単位や一部の指標だけに着目してしまい、サイト全体としての成果が改善されないケースもあります。たとえば、LPの離脱率を下げても、その前段の流入施策や後段の導線が整っていなければ意味がないでしょう“部分最適”に偏らないようにするためには、サイト全体の構造やユーザーフローを俯瞰して見ることが欠かせません。施策の優先順位も含め、全体視点を意識することが重要です。
サイト改善につなげるためのポイント

分析で得たデータを実際の改善施策に活かしていくには、継続的な仕組みと社内での共有体制が欠かせません。次に、成果につながるサイト運用の3つの視点を解説します。
定期的なモニタリング体制の構築
1回の分析で終わらせず、定期的にデータをチェックする体制を作ることで、トレンドの変化や課題の早期発見が可能になります。週次や月次での数値確認をルーチン化し、同じフォーマットでレポートを作成すれば、変化の兆しに気づきやすくなります。施策を打った後の反応を見る際にも、定期的なモニタリングは不可欠です。短期的な数値だけでなく、中長期の視点をもつことが成果につながります。
チーム間の共有とナレッジの蓄積
サイト分析の結果や改善施策の効果は、担当者だけでなく関係者全体で共有するのがおすすめです。マーケティングやデザイン、開発など各部門で分析結果を把握できれば、施策の一貫性やスピード感が向上します。また、施策ごとの成果や失敗事例をナレッジとして蓄積することで、属人化を防ぎ、組織的な改善力を高めることにもつながります。情報の整理と可視化を心がけ、全体でPDCAを回す体制を整えましょう。
PDCAを継続する
一度の改善で完了とせず、データ分析・仮説立案・実施・検証の流れでPDCAを継続的に回すことが成果の積み重ねに直結します。また、分析・改善をして終了では十分な結果が得られない場合があります。改善施策が本当に効果的だったのかを必ず振り返り、次の改善に活かす視点が重要です。PDCAを丁寧に繰り返すことで、サイト全体の質が徐々に向上していきます。
まとめ
サイト分析は、Webマーケティングやサイト運用において欠かせない要素の一つです。ただツールを使って数値を眺めるだけでは意味がなく、「なぜ分析するのか」「どのように活かすのか」という視点を持つことが成果につながります。本記事で紹介したように、定量・定性の両面からアプローチし、目的に応じて適切な手法を選ぶことがポイントです。分析から改善、検証までのサイクルを回し続けることで、継続的な成長を実現できます。地道な積み重ねこそが、ユーザー満足と成果の両立を可能にします。
「サイト分析に取り組みたいけれど、何から始めればいいかわからない」「ツールは導入しているけれど、活用できていない」と感じている方は、ぜひ一度Creative Driveにご相談ください。目的設計からデータの読み解き方、改善提案、施策の実行まで、戦略的なサイト分析を一貫してサポートいたします。現状の課題を明らかにし、成果につながる運用体制を一緒に構築していきましょう。まずはお気軽にお問い合わせください。